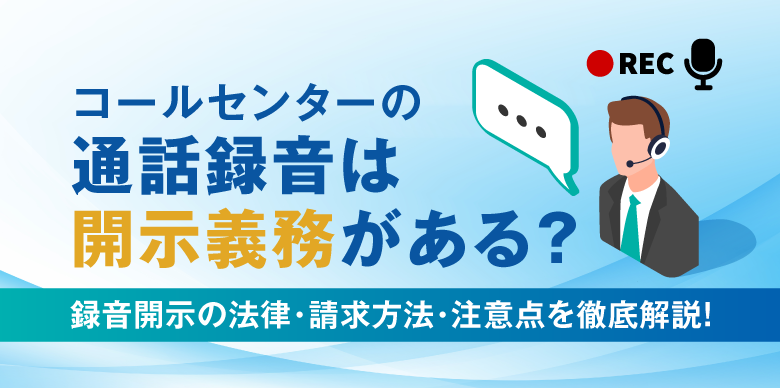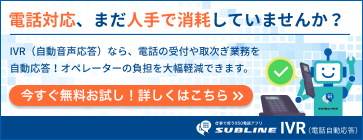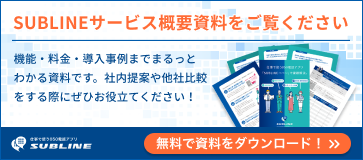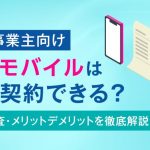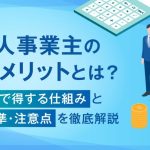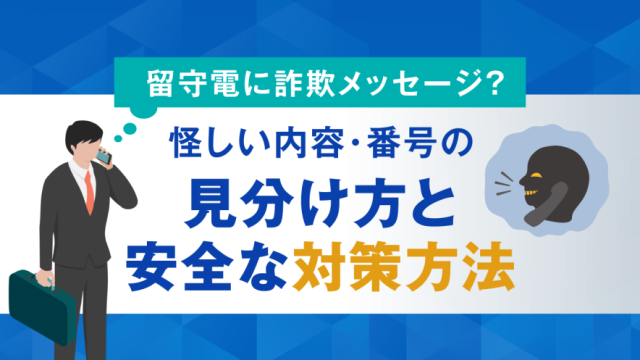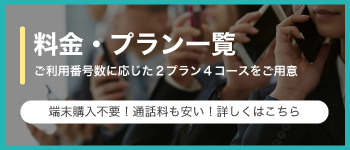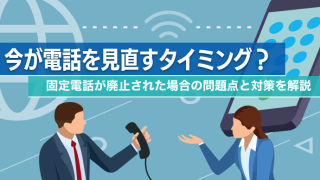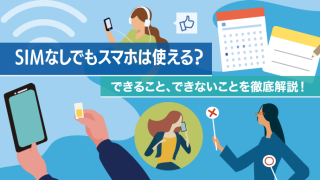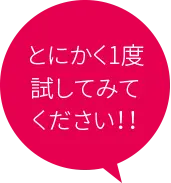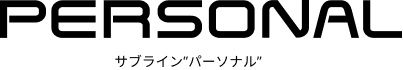本記事では、録音の開示義務や保存期間、法律的な根拠、請求手順、トラブル事例、おすすめのIVR(自動音声応答)ツールまで解説いたします。
コールセンターの通話録音は違法?合法?
近年、多くのコールセンターでは顧客との通話を録音する運用が一般的になっています。しかし、「録音されることに抵抗がある」「知らないうちに録音されていた」といった不安の声もあり、録音の合法性が疑問視されることがあります。
ここでは、コールセンターでの録音が違法かどうか、どのようなルールのもとで行われているのかを解説します。
通話録音は違法?合法?
原則として、コールセンターによる通話録音は違法ではありません。しかし、以下のようなケースでは、録音が違法と判断される可能性があります。
- 録音することを一切通知せず、密かに録音している場合でも、通話の当事者が録音する限り日本の法律上は原則として違法ではありません。ただし、録音の利用方法によっては違法性が問われる場合(故意に第三者へ漏洩させるなど)があるので注意が必要。
- 録音した情報を本人の意に反して不正利用した場合(個人情報保護法違反)
このような場合には、民事上の損害賠償請求や、個人情報保護委員会からの指導を受ける可能性もあります。
通話録音の目的と実態
コールセンターでの通話録音には、主に以下の3つの目的があります。
- 応対品質の向上:オペレーターの対応を教育や研修に活用し、サービスレベルの均質化を図る目的。
- トラブル防止・証拠保全:契約内容ややり取りの証拠として、後のトラブル防止に活用。
- 顧客満足度の分析:録音データをテキスト化・分析し、顧客ニーズや苦情傾向を把握する目的。
実際の運用では、顧客との通話はシステム上自動で録音され、一定期間保存されたのち、自動削除されるケースが一般的です。録音の有無は、冒頭のアナウンスやオペレーターによる口頭説明で伝えられます。
録音前の通知義務はあるのか?
日本の法律では、通話録音そのものに明確な通知義務は規定されていません。ただし、録音した内容を本人の同意なく第三者に提供した場合や、不適切に利用した場合は、プライバシーの侵害や個人情報保護法違反となる恐れがあります。
そのため、多くの企業ではリスク回避の観点から以下のような対応を取っています。
- IVR(自動音声応答)による録音の事前通知:「この通話は応対品質向上のため録音させていただいております」
オペレーターによる録音の口頭説明:「この通話は録音させていただきます。ご了承ください」
とくに IVR(自動音声応答)を活用した通知は、対応漏れを防ぎ、法的リスクを回避する有効な方法です。
録音データに開示義務はある?
「コールセンターで録音された通話内容を聞きたい」「トラブル時の証拠として録音を入手したい」という声は多く、録音データに開示義務があるのかどうかは重要な関心事です。
ここでは、録音データの法的位置づけや、開示が求められるケースについて詳しく解説します。
録音データは個人情報にあたるのか
結論から言うと、コールセンターでの録音データは「個人情報」に該当する場合があります。
個人情報保護法では、氏名、住所、電話番号のような特定の情報だけでなく、「特定の個人を識別できる声の録音」も、個人を識別できる要素を含む限り個人情報として扱われるとされています。
たとえば、以下のような通話録音は個人情報となる可能性があります。
- 氏名・電話番号などを話している音声が含まれている
- 発言内容と照合することで個人を特定できる
したがって、個人情報保護法の対象として、本人が録音データの開示を請求できる法的根拠となりえます。
個人情報保護法における「保有個人データ」とは
録音データが個人情報に該当したとしても、すべてが開示の対象になるわけではありません。重要なのは、それが「保有個人データ」であるかどうかです。
「保有個人データ」とは、以下の要件を満たす情報を指します。
- 組織が構造化して管理・検索できる形式で保持している
- 6か月を超えて継続的に保有するデータ
- 開示、訂正、削除などに応じる義務のある情報
一時的に記録された録音データで、保存期間が短く、本人を特定できない場合はこの定義に該当しないことがあります。
つまり、「開示請求の対象となるかどうか」は、録音の保存形式・期間・内容によって異なるため、個別に確認が必要です。
開示請求に企業が応じる義務があるケース
録音データが「保有個人データ」に該当し、本人確認が適切に行われた場合、企業は原則として開示に応じる義務があります。これは、個人情報保護法第33条に基づく権利です。
企業が録音データを開示するケースとしては、以下のような状況があります。
- 顧客が通話内容の確認を求めてきた場合
- トラブル・誤解の解消のために録音の一部提供が合理的と判断された場合
- 苦情対応や社内調査を目的に、顧客が録音を入手したいと申し出た場合
ただし、第三者の情報が含まれる録音や、業務に支障をきたすと判断される場合には一部開示や開示拒否も認められるため、すべての請求が認められるわけではありません。
通話録音の開示請求方法と手順
実際にコールセンターで録音された通話内容を確認したい場合、どのように請求すればよいのでしょうか。
ここでは、録音データの開示を希望する際の一般的なフローや注意点を、わかりやすく解説します。
まずは企業の窓口に連絡
録音データの開示を希望する場合は、まずはコールセンターや個人情報に関する問合せ窓口に連絡することが第一歩です。多くの企業では、個人情報の開示・訂正・削除に対応する専用窓口を設けています。
問い合わせ時には、以下の点を明確に伝えるようにしましょう。
- 通話を行った日時
- 使用した電話番号
- 担当者名(可能な場合)
- 通話内容の主旨(請求・申込・苦情対応など)
これらの情報が揃っていないと、録音の特定が難しく、開示に応じてもらえないことがあります。
本人確認に必要な書類とは
録音データは個人情報に該当する可能性が高いため、企業側は本人確認を徹底する義務があります。したがって、開示請求の際には以下のいずれかの書類の提出が求められることが一般的です。
- 運転免許証やマイナンバーカードなどの公的身分証明書
- 住民票や公共料金の領収書など、居住実態のわかる補足書類
- 委任状(代理人による請求の場合)
企業によっては、申請書類のテンプレートを用意している場合もあるため、事前にウェブサイトや電話で確認することが重要です。
開示にかかる日数や費用の目安
録音データの開示には、申請から数日〜数週間程度かかるのが一般的です。企業によっては「10営業日以内に回答」といった社内規定を設けているところもあります。
また、録音の提供には以下のような形式が考えられます。
- 音声データをCDやUSBで提供
- 書き起こし(テキスト)データでの提供
- 通話内容の一部要約を文章で提示
費用については、多くの企業で無料対応が基本ですが、郵送費や媒体費(CD・USB)などの実費相当分を請求される場合もあります。請求の有無や金額については、事前に企業側に確認しましょう。
録音開示を企業が拒否できる正当な理由
個人が録音データの開示を請求した場合、企業は原則として個人情報保護法に基づき遅滞なく応じる義務があります。
ただし、すべての請求に無条件で応じる必要はなく、法令で定められた例外事由がある場合には開示を拒否できます。
ここでは、企業が正当な理由で開示を拒否できる代表的なケースを紹介します。
開示が第三者の利益を害する場合
録音内容に他の顧客や従業員など第三者の個人情報が含まれている場合、その部分の開示はプライバシーの侵害につながる可能性があります。
たとえば以下のようなケースでは、開示を制限または拒否することが正当化されます。
- 他の顧客の氏名や住所、注文情報が含まれている
- オペレーター個人の私的な情報が含まれている
- 複数人の会話が重なっているため編集が困難
このような場合には、該当部分をマスキング(音声カット)したうえで一部開示とするか、やむを得ず全体の開示を拒否することも認められています。
業務遂行に著しい支障がある場合
録音データの開示が企業の通常業務に支障をきたすと判断される場合、企業には開示を拒否できる正当な理由があるとされています。
たとえば以下のような事例が考えられます。
- 録音の特定や編集に過度な工数がかかる
- 開示請求の内容が嫌がらせや業務妨害を目的としている
- 同一人物から繰り返し・大量の請求がある
こうした場合、企業側は業務効率やセキュリティの観点から、合理的な範囲での対応にとどめることが許されるとされています。
保有期間を過ぎて録音が残っていないケース
録音データは永続的に保存されるものではなく、多くの企業では一定期間経過後に自動削除される設定になっています。
たとえば以下のような保存期間の目安が一般的です。
- 通常の通話録音:30日〜90日程度
- 金融機関や保険会社などの重要データ:6か月〜1年程度
そのため、開示請求のタイミングが遅すぎると、すでに録音が削除されていて開示不能となっているケースもあります。これについては企業側に責任はなく、開示拒否は正当化されます。
録音データの保存期間と企業の義務
録音データの開示請求において「すでに録音が削除されている」と回答されることがあります。これは企業側の義務違反なのでしょうか?
ここでは、録音の保存期間に関する一般的な慣行と、企業に課せられる保存義務の有無について解説します。
法律で定められた保存義務はあるのか
実は、日本の法律においてすべてのコールセンターに録音保存を義務付ける明確な法令は存在しません。しかし、業種によっては特別法や行政指導により保存期間が定められている場合があります。
例えば
- 金融商品取引業者は、「金融商品取引法施行規則」により、勧誘時の通話録音を原則1年間保存するよう義務付けられています。
- 保険業者も同様に、一定期間の録音保存が「業務運営方針」として求められています。
一方で、一般のECサイトやカスタマーサポートなどのコールセンターには、保存義務そのものはないことがほとんどです。ただし、トラブル予防の観点から、多くの企業が任意で録音保存を行っています。
一般的な保存期間の目安
企業によって保存期間はさまざまですが、以下が一般的な目安とされています。
| 業種・業態 | 録音保存期間の傾向 |
| 一般的なBtoCコールセンター | 約30~90日 |
| クレジットカード会社 | 約6ヶ月〜1年 |
| 金融・保険関連 | 約1年(法令または自主規定) |
| 公共機関・自治体 | 3ヶ月~1年(条例や運用規定による) |
保存期間が短い理由は、サーバー容量の制限や運用コスト、プライバシー保護の観点からです。開示請求を検討する場合は、なるべく早めの問い合わせが望まれます。
開示請求を見越した適切な運用体制とは
企業としては、録音データの開示請求に備えた適切な保存・管理体制の構築が重要です。具体的には、以下のような運用体制が推奨されます。
- 録音保存期間の明文化と社内共有
- 開示請求への対応マニュアルの整備
- 録音データの検索性を高めるシステムの導入
- 一部の録音だけ長期保存するアーカイブ機能の活用
- 定型業務のIVR(自動音声応答)化による録音回避も選択肢
また、顧客への事前案内において「録音は○日間保存します」「録音内容に関するお問い合わせは○○まで」と明記することで、トラブルの未然防止にもつながります。
企業向け:コールセンター運営で注意すべき録音対応のポイント
コールセンターにおける録音対応は、単なる品質管理の手段ではなく、法令順守・顧客対応の信頼性確保・トラブル防止の要でもあります。
ここでは、企業が押さえておくべき録音対応の実務ポイントと、ツール活用の工夫について解説します。
開示請求に備えた録音データの管理体制
顧客からの録音データ開示請求にスムーズに対応するためには、録音データの検索性・保全性を確保した管理体制の構築が不可欠です。
たとえば以下のような工夫が必要です。
- 通話記録と連動した顧客管理(CRM)との統合
- 「誰が・いつ・どの端末からアクセスしたか」が分かるログの保存
- 保存期間や削除タイミングの明文化
- 顧客からの請求に備えた対応フローの整備(社内マニュアル)
こうした体制を整えておくことで、不測のトラブル時にも迅速・適正に対応でき、企業の信頼性向上につながります。
開示に関する社内マニュアル整備の必要性
録音データの開示は、個人情報保護法や社内規定に基づいた慎重な判断と運用が求められます。オペレーターや管理部門が混乱しないよう、以下のような社内マニュアルを整備しておくと安心です。
- 開示請求を受けた際の一次対応フロー
- 本人確認手続きと必要書類の案内テンプレート
- 一部開示や開示拒否の判断基準(法的根拠付き)
- 対応履歴や開示記録の保存方法
こうしたマニュアルが整備されていれば、現場任せにせず、組織的かつ法的リスクを抑えた対応が可能になります。
IVR(自動音声応答)を活用した電話対応の効率化
コールセンターにおける対応の信頼性と効率を高めるために、多くの企業がIVR(自動音声応答)を導入しています。とくに通話件数が多いコールセンターにおいては、IVRによってリスク管理と業務効率が大きく改善されます。
ここでは、おすすめのツールSUBLINE(サブライン)をご紹介します。
IVR(自動音声応答)とは?電話対応の強い味方
IVRとは、「Interactive Voice Response」の略で、発信者の入力に応じて音声案内や着信振り分け、録音の自動開始などを行うシステムです。たとえば「1番:契約内容の確認、2番:解約手続き」といった案内に従って発信者をオペレーターに直接つなげてくれる仕組みです。
このIVRを活用することで、通話分類が自動化され、対応ミスを防げるようになります。
SUBLINE(サブライン)で電話対応を強化
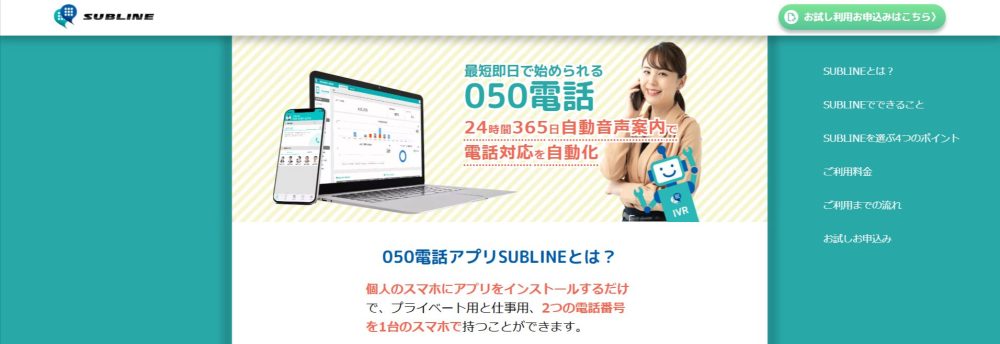
SUBLINE(サブライン)は、IVRを搭載しているのでかかってきた電話に対し自動音声ガイダンスで受付、対応することが可能です。たとえば「この通話は応対品質向上のため録音させていただいております」といったメッセージを事前に設定しておくだけで、人的トラブルや法的リスクの軽減につなげることができます。
このように何かしら音声案内を設定しておくことで「誰も電話に出ない」「何の案内もない」といったネガティブな印象を未然に防ぐことができます。また、あらかじめ用件を選択してもらうメニュー形式(例:1番は予約、2番はキャンセル )を設定すれば、後からメールで対応する際にも優先順位をつけやすくなります。
よくある質問(FAQ)
録音の取り扱いや開示義務については、個人・企業ともに多くの疑問を抱えています。
ここでは、検索ニーズの高い質問をピックアップし、実務にも役立つ形でわかりやすく回答します。
コールセンターが勝手に録音するのは違法ですか?
いいえ、通話の録音そのものは違法ではありません。日本の法律では、通話を録音すること自体を禁じる規定はありません。ただし、録音の事前通知を行わず、密かに録音する場合は、プライバシー権の侵害とされる可能性があるため注意が必要です。
そのため、ほとんどの企業では「この通話は録音されます」などのアナウンスを通話開始前に行っています。
コールセンターで音声を録音していいですか?
原則として問題ありません。企業側の正当な業務目的(応対品質向上・トラブル防止など)に基づく録音は合法です。ただし、通話相手に対して録音の旨を明示することが望ましいとされています。
明示せずに録音すると、トラブル時に「勝手に録音された」とクレームになることもありますので、できる限り事前に伝えましょう。
電話の録音は通知義務がありますか?
法的には明確な通知義務はありませんが、プライバシー保護の観点から、実務上は通知が推奨されます。
特にBtoCの窓口業務においては、「録音されることを知らなかった」ことが後のクレームや信用問題につながるため、IVRなどを使って事前に通知するのが一般的な運用です。
録音された通話内容を開示してもらえますか?
録音データが個人情報に該当し、かつ保有個人データとして管理されている場合、本人は開示請求を行うことができます。企業側は合理的な範囲でこれに応じる義務があります。
ただし、第三者の情報が含まれている場合や、業務に支障をきたすと判断される場合など、正当な理由があれば一部開示や拒否されることもあります。
開示請求を拒否された場合、どうすればいいですか?
まずは企業に拒否理由の開示を求めてください。それでも納得できない場合は、以下の対応が可能です。
- 消費生活センターなどの行政機関への相談
- 個人情報保護委員会への申立て
- 弁護士を通じた法的措置(民事請求)
ただし、録音がそもそも削除済みで存在しない場合など、企業に過失がないケースもあるため、慎重な対応が求められます。
録音データの保存期間はどれくらい?
保存期間は企業や業種によって異なりますが、一般的には30日〜90日程度が多く、金融機関などでは半年〜1年保存するケースもあります。保存期間を過ぎると録音は自動削除されるため、開示請求はできるだけ早めに行うのがベストです。
開示請求できるのは本人だけですか?
基本的に開示請求ができるのは本人に限られます。ただし、法定代理人(未成年者の親など)や、正当な委任状を持つ代理人であれば、本人に代わって請求することが可能です。
その際には、本人確認書類と代理人の本人確認書類、および委任状の提出が求められます。
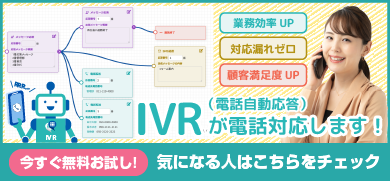
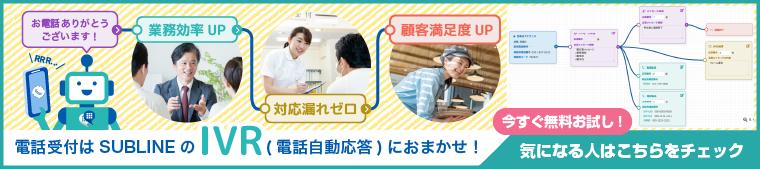
不要な電話対応にサヨナラ!
WEBで完結!無料お試しが可能です!
PROFILE

-
株式会社インターパーク/SUBLINEプロジェクトリーダー・マーケティング担当
中途で株式会社インターパークに入社。
仕事で使う050電話アプリSUBLINE-サブライン-のカスタマーサポート担当としてアサイン。
カスタマーサポートを経て、現在は事業計画の立案からマーケティング担当として事業の推進・実行までを担当。
過去、学生時代には2年間の海外留学を経験。