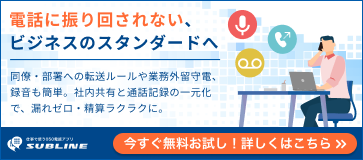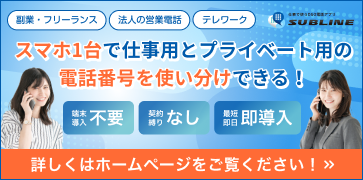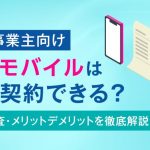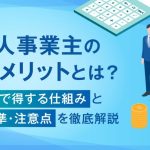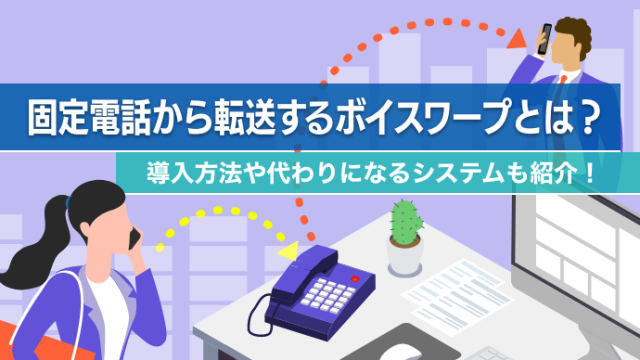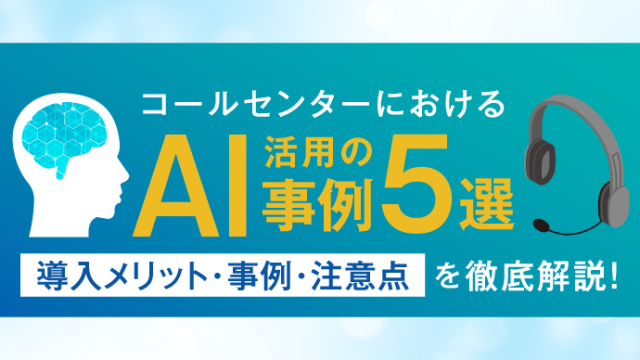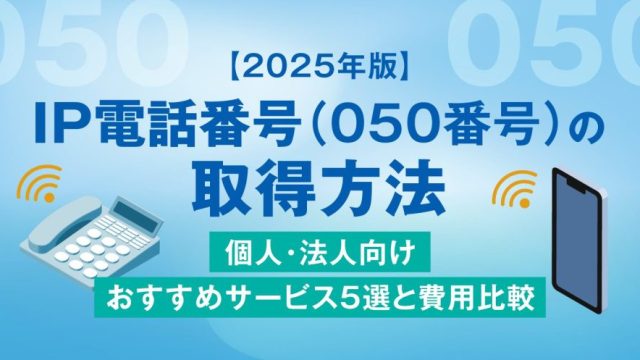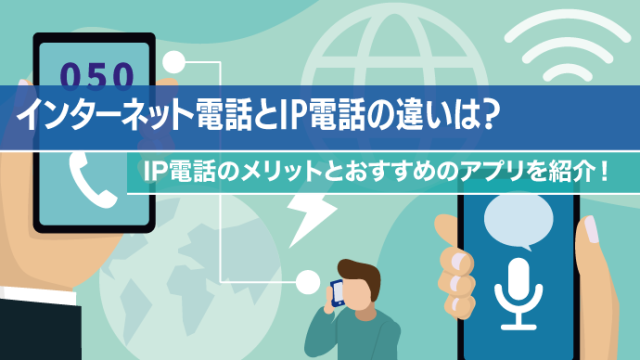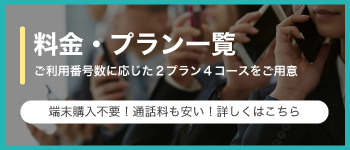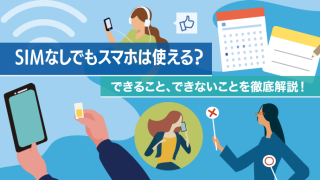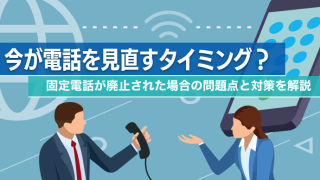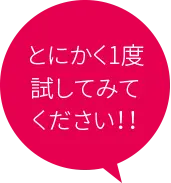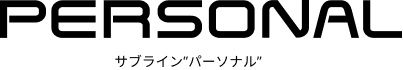本記事では、法人携帯導入の必要性やメリット・デメリット、導入手順やコスト、さらにおすすめのIP電話サービスまでご紹介します。
法人携帯の導入が注目される背景とは
近年、多くの企業が「法人携帯」の導入を進めています。かつては限られた業種での利用が主でしたが、テレワークの拡大やコンプライアンス意識の高まりにより、今や業種・規模を問わず導入が進んでいます。
ここでは、法人携帯がなぜ注目されているのか、その背景を紐解きます。
なぜ今、法人携帯が必要なのか?
法人携帯が必要とされる理由の一つは、業務と私用の線引きが求められているからです。個人携帯を業務で使用するケースでは、以下のような問題が発生します。
- 社員が私用と業務の通話・データ利用を分けづらい
- 退職や異動時に取引先との連絡が途絶える可能性がある
- 情報漏えいや不正利用のリスクがある
法人携帯を導入することで、業務用の番号・端末を会社が一元管理できるようになり、これらのリスクを低減できます。加えて、顧客対応力の向上や、勤怠・業務管理との連携など、働き方のデジタル化に対応する基盤としても重要な役割を果たします。
個人携帯やBYOD運用との違いとリスク
BYOD(Bring Your Own Device)とは、社員が自分のスマートフォンを業務に活用する運用形態です。初期コストを抑えられる点ではメリットもありますが、以下のリスクが伴います。
- 業務中の私用利用が増え、集中力や生産性に悪影響
- 端末の紛失時に企業情報が流出するリスク
- 退職後のデータ削除や回収が困難
- セキュリティ対策が個人任せになりがち
一方、法人携帯であればMDM(モバイルデバイス管理)などを通じて端末の遠隔制御や利用制限が可能です。企業のセキュリティポリシーに準じた管理ができる点が大きな強みです。
テレワークや外出先対応でのニーズ拡大
2020年以降の新しい働き方により、オフィスにとどまらない業務スタイルが常態化しました。営業職や現場スタッフはもちろん、カスタマーサポートなども自宅や外出先から対応する必要が出てきています。
法人携帯を導入することで、以下のような柔軟な運用が可能になります。
- オフィスの固定電話番号を携帯端末に転送
- 拠点をまたぐ通話・チャット・共有ツールとの統合
- モバイルアプリやクラウド電話との連携
こうした背景から、業務専用端末としての法人携帯の導入は、企業の競争力を維持するうえでも不可欠な選択肢となっています。
法人携帯導入のメリットとデメリット
法人携帯の導入は、企業運営において多くの利点をもたらします。しかし一方で、導入前に知っておくべき注意点も存在します。
ここでは、実際に導入することで得られるメリットと、想定しておくべきデメリットについて、具体的に解説していきます。
業務効率化・顧客対応力の向上
法人携帯の最大のメリットは、業務効率の向上と顧客対応力の強化です。
- 社員一人ひとりに会社支給の端末を配布することで、業務連絡の即時性が向上します。
- 社内での連絡ツールやビジネスチャットとの連携がしやすくなり、チーム間の情報共有もスムーズに。
- 顧客との通話においても、業務専用の番号を使うことで信頼性を高め、取引先とのやりとりが明確化されます。
- 通話履歴や対応内容の管理も可能になり、CS(カスタマーサポート)品質の向上にもつながります。
たとえば、営業職であれば、外出先からの電話対応を自社番号で行えることで、見込み客との接点を逃さず即対応できます。
社員のプライバシー保護と管理強化
個人携帯を業務に使うと、社員のプライベートと業務の境界が曖昧になり、以下のような課題が発生します。
- 私用中に業務連絡が入るストレス
- 退職後の情報流出リスク
- 通話履歴や連絡先が個人のスマホに残ることへの懸念
法人携帯を導入すれば、業務と私用の分離が可能となり、社員のプライバシーが守られるだけでなく、企業としての情報保護体制も強化されます。加えて、MDM(モバイルデバイス管理)を導入すれば、位置情報の確認や端末の遠隔ロック・ワイプなども可能となり、ガバナンスの強化にもつながります。
コストや運用面での注意点
一方で法人携帯の導入には当然ながらコストが発生します。主な内訳としては、
- 初期費用(端末代、設定作業費など)
- 月額料金(基本使用料・通話料・データ通信料)
- 保守・サポート費用(MDMライセンス費など)
特に、社員数が多い企業ほどトータルコストが膨らむ傾向があるため、キャリア選定やプランの最適化が重要です。また、以下のような運用課題も発生しがちです。
- 利用状況の把握・管理が煩雑になる
- 紛失時の初動対応が遅れると情報流出リスクが高まる
- プランの見直しを怠ると、無駄な通信コストが発生
コスト対策としては、中古端末の活用やIP電話との比較検討も有効です。
紛失・情報漏えいリスクと対策
また業務用スマートフォンには、顧客情報・業務データ・メール・社内チャットなど、非常に重要な情報が保存されます。そのため、端末の紛失や盗難が起きた場合は、重大な情報漏えい事件に発展する可能性も。
対策としては、
- MDMでの遠隔ロック・ワイプの設定
- 端末のロック解除パスワード・生体認証の義務化
- 社内ルール(紛失時の報告・再発防止教育)の徹底
- 暗号化やVPN利用による通信セキュリティの強化
このように、導入と同時にセキュリティポリシーの整備と教育を行うことで、リスクを最小限に抑えることが可能です。
法人携帯の選び方と比較ポイント
法人携帯の導入を成功させるには、「どの端末・どのプランを選ぶか」「契約形態はどうするか」といった判断が重要です。選び方を誤ると、コストが無駄に膨らんだり、業務に合わない仕様で使いづらくなったりすることもあります。
ここでは、導入時に比較・検討すべき主要なポイントを解説します。
機種選定のポイント(iPhone/Android/ガラケー)
法人携帯では、業務内容や利用環境に合わせて端末を選ぶことが重要です。
- iPhone:操作性やブランド力が高く、ビジネスアプリとの互換性も豊富。海外出張の多い企業や役員クラスで好まれる傾向。
- Android:機種の選択肢が幅広く、価格帯も柔軟。カスタマイズ性や業務用アプリとの親和性が高いため、現場業務や営業職に多く採用される。
- ガラケー(フィーチャーフォン):コストが低く、バッテリー持続時間も長いため、通話が中心の現場作業員や短時間利用のスタッフに適している。
企業の業務スタイルに応じて、「誰がどの場面で使うのか」を明確にしたうえで最適な機種を選定することが大切です。
通信プランの選び方|通話・データ・海外対応
法人携帯の費用は、選ぶプランによって大きく変わります。
- 通話中心の業務 → 無制限か大容量の通話プランを選択
- 外出先でのデータ利用が多い職種 → 大容量データプランやテザリング対応を重視
- 海外出張や国際電話が多い企業 → 国際ローミングや海外定額プランを比較
社員によって利用状況が異なるケースも多いため、用途別にプランを分ける「ハイブリッド運用」もコスト削減に有効です。
契約形態の違い(キャリア/MVNO/一括・分割)
法人携帯の契約には大きく2つの選択肢があります。
- キャリア契約(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクなど)
→ 安定した通信品質、法人専用サポート窓口あり。ただし費用はやや高め。 - MVNO契約(格安SIM事業者)
→ 低コストで導入可能。小規模企業やスタートアップで人気。ただし大規模運用や通信品質面では注意が必要。
そして端末購入方法も「一括購入」か「分割払い」で大きく異なります。導入初期にコストを抑えるなら分割、長期利用を前提にするなら一括購入のほうが割安になることもあります。
管理体制とセキュリティ対策(MDM/MAM/MCMなど)
法人携帯の導入において見落とされがちなのが管理とセキュリティ対策です。
- MDM(モバイルデバイス管理):端末の遠隔ロック・データ消去・利用制限が可能
- MAM(モバイルアプリ管理):業務アプリのみ利用可能に設定
- MCM(モバイルコンテンツ管理):社内文書・データの利用制御を実施
これらを導入すれば、社員が紛失した場合でも迅速に対応可能です。特に情報セキュリティを重視する企業では、法人携帯導入と同時に管理ツールの導入をセットで検討することが必須です。
導入から運用までのフローを解説
法人携帯を導入する際は、単に端末を購入して配布すればよいわけではありません。導入前の準備から契約・設定、運用後の管理までをしっかり設計することで、コストの無駄やセキュリティリスクを防ぎ、スムーズに業務に活かすことができます。
ここでは、導入から運用までの流れを具体的に解説します。
導入前の準備|台数・用途・予算の見積もり
法人携帯導入の第一歩は、自社に必要な利用台数や用途を明確化することです。
- 営業職向けに「通話中心の端末」が必要なのか
- データ利用が多い部署に「大容量プラン」を割り当てるべきか
- 社員全員に配布するのか、それとも一部の部署に限定するのか
これらを整理したうえで、月額予算と初期費用の上限を決めておくことが重要です。さらに、通信キャリアの候補を複数ピックアップし、見積もりを比較検討することで、コスト効率の高い導入が可能になります。
契約・キッティング・開通までのステップ
導入準備が整ったら、次のステップは契約手続きと端末の設定(キッティング)です。
- 契約:法人名義で契約を行い、必要書類(登記簿謄本、印鑑証明など)を提出
- 端末準備(キッティング):OSアップデート、アプリインストール、セキュリティ設定をまとめて実施
- 開通作業:SIMカード挿入や回線開通テストを行い、実際に通話や通信ができる状態に設定
法人携帯は社員数が多いと作業量も増えるため、外部のキッティング代行サービスを活用するとスムーズです。
利用開始後の運用・管理の実務ポイント
導入後は、日々の運用管理が欠かせません。特に注意すべきは以下の点です。
- 利用状況のモニタリング:通信料・通話時間・データ使用量を定期的にチェック
- セキュリティ対応:紛失や盗難発生時にはMDMで即時ロックや遠隔消去を実施
- プランの見直し:利用実態に合わせて通話プランやデータ容量を適宜調整
- ライフサイクル管理:端末の故障・買い替え・退職社員からの回収フローを整備
これらを徹底することで、コスト最適化とセキュリティ強化を両立できます。特に中長期的な視点で見ると、運用体制を整えることが法人携帯活用の成否を分けるポイントになります。
法人携帯のコスト比較と見積もり例
法人携帯を導入する際、多くの企業が気にするのが「結局いくらかかるのか?」というコスト面です。初期費用・月額料金・維持費は契約内容によって大きく異なるため、導入前にシミュレーションしておくことが欠かせません。
ここでは、法人携帯のコスト構造をわかりやすく整理し、比較のポイントを解説します。
初期費用と月額料金の目安
法人携帯の導入にかかる費用は大きく2つに分かれます。
- 初期費用
端末代金(0〜5万円程度/台が一般的)、契約事務手数料(3,000〜3,850円/台)、設定作業費(数千円程度/台) - 月額料金
基本料金(500〜1,500円/台)、通話料金・データ通信料金(合計で1,000〜6,000円/台が相場。キャリア・MVNOで幅あり)
例えば10台を導入する場合、初期費用は10万〜50万円程度、月額は約1万〜6万円程度が目安となります。キャリアやMVNOを選ぶかで大きく変動するため、事前に見積もりを複数取得することが重要です。
プラン別・キャリア別の料金比較表
法人携帯のコストを最適化するには、キャリアごとの特徴や料金プランの違いを把握することが欠かせません。
- 大手キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)
→ 通信品質やサポート体制が充実。ただし料金はやや高め。 - MVNO(格安SIM事業者)
→ 月額1,000〜3,000円程度で利用可能。大幅なコスト削減が可能。コスト重視の企業や小規模事業者に人気。
具体的な比較例
- ドコモ法人プラン:月額約5,000円/台(音声+データ10GB)
- MVNO法人プラン:月額約2,000円/台(音声+データ10GB)
同じ条件でも、キャリアとMVNOで月額2倍以上の差が出ることも珍しくありません。
中古端末やサブブランド活用によるコスト削減
コストを抑えるもう一つの方法が、中古端末やサブブランドの活用です。
- 中古端末の導入
耐用年数が残っている端末を中古で購入すれば、1台あたりの端末費用を半額以下に抑えられる場合があります。 - サブブランド(ahamo、UQモバイル、ワイモバイルなど)
大手キャリアの通信品質を確保しつつ、低価格プランを利用可能。
さらに、IP電話サービスを組み合わせることで、通話コストをさらに削減できます。導入コストと運用費の両面で工夫を凝らすことで、法人携帯のコストは大幅にコントロールできます。
法人携帯の代替手段|SUBLINE(サブライン)なら低コスト&即導入!
法人携帯の導入は多くの企業にメリットをもたらしますが、初期費用や管理負担がネックになるケースも少なくありません。
そんなときにおすすめのツールが、050電話アプリSUBLINE(サブライン)です。
SUBLINE(サブライン)とは?スマホで業務用番号が使えるIP電話

SUBLINE(サブライン)は、お手持ちのスマホにアプリをインストールするだけで、プライベート番号の他にもう一つ、仕事用の050電話番号が持てるサービスです。
個人のスマホにアプリを入れるだけなので、端末を新たに用意する必要がありません。
低コストかつ短期間で法人携帯を導入したい方に最適です。
また、1名から100名以上まで、企業規模問わず導入しやすいのも特徴です。
詳しくは公式サイトをご覧ください。
公式サイト https://www.subline.jp/
よくある質問(FAQ)
法人携帯を導入する際、多くの企業が共通して抱く疑問があります。
ここでは、導入検討中によく寄せられる質問に具体的に回答していきます。
法人携帯を導入するメリットは?
法人携帯を導入することで、業務と私用の分離が明確になり、社員のプライバシー保護と企業の情報管理が両立できます。また、会社番号での発着信により顧客からの信頼性も高まり、通話履歴や契約情報を会社で一元管理できる点も大きなメリットです。
携帯を法人契約するデメリットは?
デメリットとしては、初期費用や月額コストの発生、さらに台数が増えるほど管理負担が大きくなる点が挙げられます。また、紛失時には情報漏えいリスクがあるため、セキュリティルールやMDM導入が必須です。
法人で携帯を契約するにはどうすればいいですか?
法人携帯の契約には、登記簿謄本や印鑑証明などの法人書類と、担当者の本人確認書類が必要です。キャリアや代理店の法人窓口を通じて見積もりを取得し、契約台数・プランを決定するのが一般的な流れです。小規模事業者なら、MVNOやサブブランドの法人プランを活用するのもおすすめです。
法人携帯の導入率は?
業種や規模によって差はありますが、近年は中小企業でも導入が一般化しています。特に営業職や外出が多い企業、テレワークを導入している企業では、法人携帯の導入率が高まっています。
法人携帯は1台からでも契約できますか?
はい、可能です。大手キャリアでも1台から法人契約できるプランがあり、個人事業主や小規模企業にも対応しています。ただし、台数が多いほど割引や特典が適用されるケースが多いため、長期的に複数台導入を見据えて検討するとよいでしょう。
紛失した場合の対応はどうなりますか?
紛失や盗難が発生した場合、速やかにキャリアや管理者に連絡し、回線の停止や端末の遠隔ロックを行います。MDMを導入していれば、遠隔からデータを消去することも可能です。初動対応を迅速に行うことが、情報漏えいを防ぐカギとなります。
法人携帯は社員のプライベート利用を制限できますか?
可能です。MDMや利用規程を導入することで、業務アプリ以外の使用を制限したり、アプリのインストールを制御したりできます。これにより、社員の私的利用を抑制し、通信コストやセキュリティリスクを軽減できます。
法人携帯とIP電話(SUBLINE)はどう違いますか?
法人携帯はキャリアと契約し、物理端末を配布して利用する形態です。一方、SUBLINEは既存のスマホにアプリを入れるだけで会社番号を利用できるIP電話サービスです。法人携帯よりも初期費用が安く、テレワークや小規模事業者に適しています。用途や規模に応じて、両者を使い分けるのが効果的です。
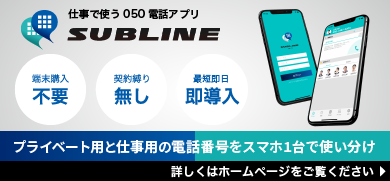

無料でお試しいただけます!
WEBで完結!最短即日で導入完了!
PROFILE

-
株式会社インターパーク/SUBLINEプロジェクトリーダー・マーケティング担当
中途で株式会社インターパークに入社。
仕事で使う050電話アプリSUBLINE-サブライン-のカスタマーサポート担当としてアサイン。
カスタマーサポートを経て、現在は事業計画の立案からマーケティング担当として事業の推進・実行までを担当。
過去、学生時代には2年間の海外留学を経験。