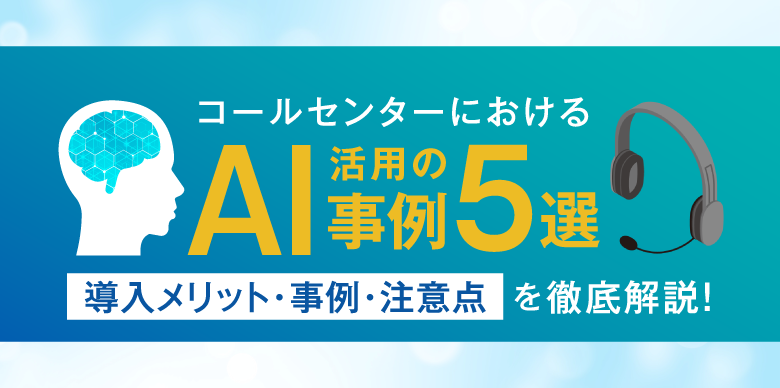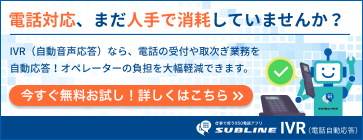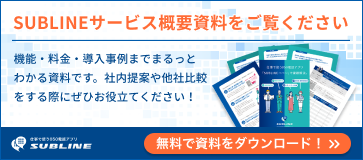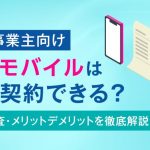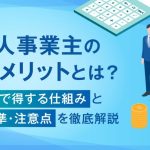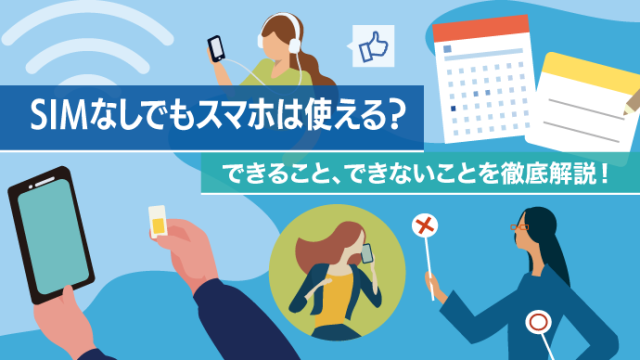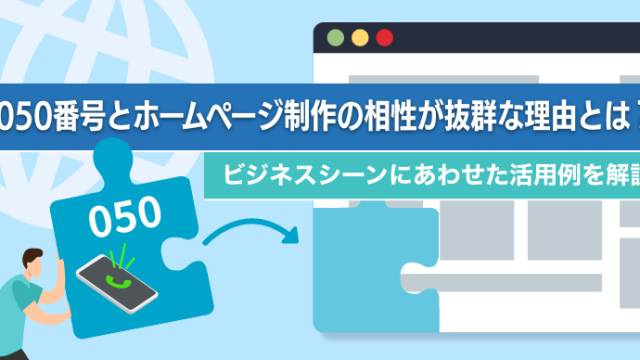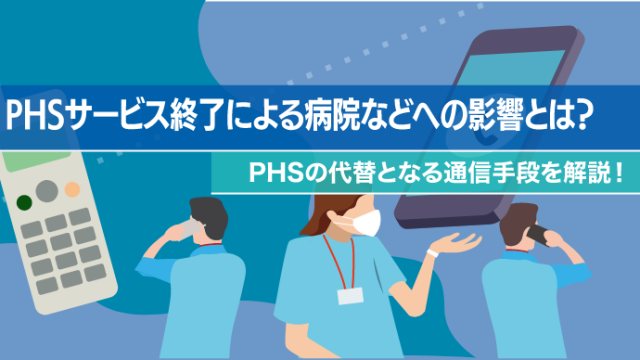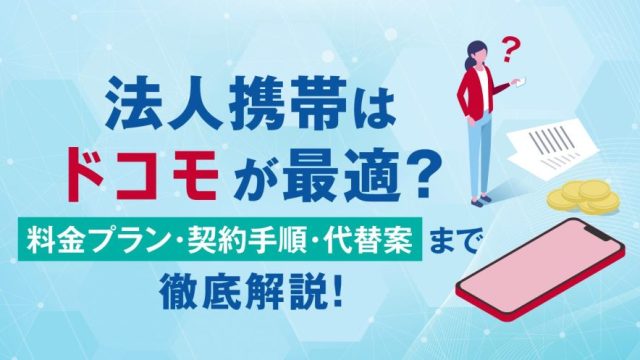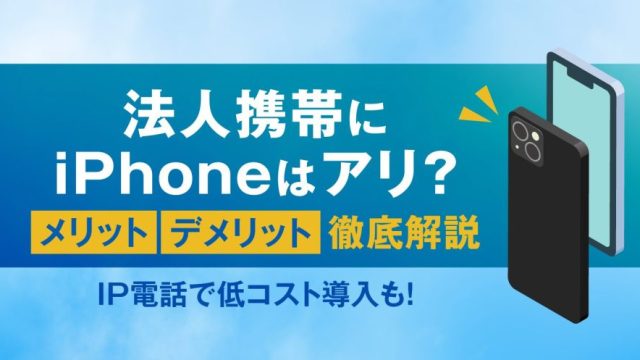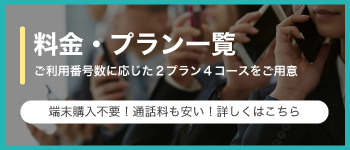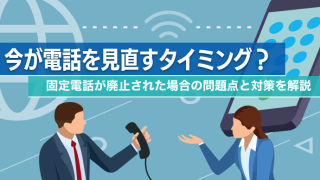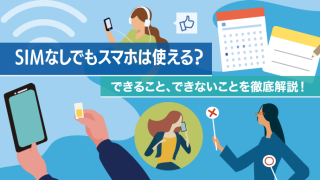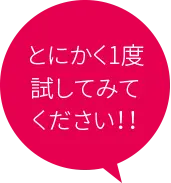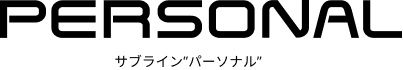本記事では、コールセンター業務にAIを導入するメリット・デメリットから、導入手順、活用法、代表的な事例を5つご紹介します。
音声認識やチャットボットの導入を検討中の方必見。人手不足・コスト課題を解決につながるヒントが見つかるかもしれません。
ぜひご一読ください。
AI導入が進む背景とは?
AIの進化とともに、コールセンター業界でもAI活用の動きが急速に進んでいます。背景には、業務の複雑化や人手不足、顧客ニーズの多様化といった構造的な課題が存在します。また、コロナ禍による非対面業務の拡大や、世の中全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の流れもAI導入を後押ししています。
ここでは、AI活用が進む背景を様々な観点から解説します。
コールセンター業界が抱える課題
コールセンターは、企業と顧客をつなぐ重要な接点ですが、現場では「応答率の低下」「対応品質のばらつき」「属人化による教育コストの増大」など、深刻な課題が山積しています。特に、問い合わせ件数の増加と人手不足が重なると、待ち時間の長期化やクレーム増加を招き、顧客満足度の低下につながります。
こうした背景から、業務の自動化や標準化を実現できるAIへの関心が高まっているのです。
人材不足とコスト削減ニーズの高まり
日本の労働人口減少により、コールセンター業界でも採用難が深刻化しています。加えて、非正規人材の入れ替わりが激しいため、教育・研修のコストも無視できません。そこで、一次対応やFAQなどの定型業務をAIに任せることで、人件費の削減だけでなく、オペレーターをより高度な業務に集中させる体制が求められています。AIは“省人化”のツールというより、“人を活かすための仕組み”として注目されています。
デジタルトランスフォーメーション(DX)との関係性
多くの企業が「デジタル化=チャットボット導入」と捉える傾向にありますが、AIの導入は単なるツール導入ではなく、業務の再設計や組織改革を伴う「DX戦略の一環」として位置づけられています。実際に、AI導入によって取得できるデータを活用し、顧客インサイトを深めたり、応対品質を定量的に可視化する企業も増加中です。AIは単なる業務効率化ではなく、CX(顧客体験)の質を上げるための戦略的資産になりつつあります。
コールセンターにAIを導入するメリット
AIの導入によって、コールセンターの業務は単に効率化されるだけでなく、顧客対応の質も大きく向上します。
ここでは、AIが実現する主なメリットを4つの観点から詳しく解説します。
①業務効率化:24時間365日の対応が可能に
AIを活用することで、コールセンターは24時間365日稼働できる体制を構築できます。特にチャットボットや音声ボットを活用すれば、深夜や休日でも顧客からの問い合わせに即時対応が可能となります。これにより、応答遅延による顧客のストレスを軽減でき、企業への信頼感が向上します。人間が対応できない時間帯をAIがカバーすることで、対応窓口の「空白時間ゼロ」を実現できます。
②人件費の削減と業務の標準化
AIによる自動応答や業務ナビゲーションの導入は、問い合わせ対応の工数を大幅に削減し、人件費の抑制に直結します。また、どの顧客にも一貫した対応が可能になり、応対品質のばらつきを防げる点も大きな利点です。マニュアルやナレッジベースに基づく対応をAIが担うことで、オペレーターの習熟度による品質差が解消され、センター全体の業務標準化が進みます。
③応対品質の向上とナレッジの共有
AIは、過去の応対履歴やFAQデータをもとに最適な回答を提示できるため、スピーディかつ的確な対応が可能です。これにより、顧客の満足度が向上するとともに、オペレーターも自信を持って対応できる環境が整います。さらに、AIが日々の応対ログを蓄積・学習することで、ナレッジの質と量が向上し、新人オペレーターへの教育にも活用できます。
④応対ログの自動収集・分析による改善
AIは、通話内容やチャット履歴などの応対ログを自動で記録・分析することができます。これにより、よくある問い合わせの傾向やクレームの発生ポイントなどを可視化でき、センター運営の改善策を迅速に講じることが可能になります。また、KPI達成度のモニタリングにも活用でき、データドリブンな運営体制を構築する第一歩となります。
一方で気をつけたいAI導入のデメリット
しかし、AI導入には多くのメリットがある一方で、課題やリスクも存在します。
ここでは、実際に導入を検討する際に企業が直面しやすいデメリットや注意点を解説します。導入後に「こんなはずではなかった」とならないためにも、事前に押さえておくことが重要です。
複雑な問い合わせへの対応は依然として困難
AIはFAQなどの定型的な問い合わせには高い精度で対応できますが、イレギュラーな内容や感情を伴う相談には限界があります。たとえば、「トラブルが起きた背景を細かく説明してほしい」「特別な配慮が必要なケース」などには、まだ人間オペレーターの判断力や共感力が求められます。AIは万能ではなく、あくまで“補完役”であるという認識が重要です。
顧客満足度が下がるリスクも
AIによる自動対応が便利な反面、「たらい回しにされる感じがする」「人間に話したいのに繋がらない」といった不満の声も少なくありません。特に高齢者やデジタルに不慣れな層にとっては、AIとの対話がストレスになることもあります。すべてを自動化するのではなく、オペレーターへの“スムーズな引き継ぎ”や“有人対応の選択肢”を残すことが、満足度低下を防ぐポイントです。
初期導入コストや社内調整のハードル
AIツールの導入には一定の初期費用がかかるほか、既存のシステムや業務フローとの連携、データ整備、人材育成など、多くの準備が必要です。特に中小企業では「効果はあるとわかっていてもリソースが足りない」といったジレンマに陥りがちです。また、現場のオペレーターが「AIに仕事を奪われるのでは」と不安を感じるケースもあり、導入には丁寧な社内コミュニケーションが求められます。
導入前に押さえておきたいポイントと注意点
AIをコールセンターに導入する前には、単にツールを選ぶだけではなく、自社の体制・業務プロセス・人材スキルなど多面的な視点から検討が必要です。
ここでは、失敗しない導入のために確認すべき3つのポイントを解説します。
自社の業務フローとの整合性確認
AIツールはどれほど高性能でも、現場の業務フローと適合していなければ期待した効果を発揮できません。たとえば、「よくある質問への対応」は自動化できても、対応が複雑に分岐するフローには人手が必要です。現場のヒアリングを行い、どこにAIを導入するのが最も効果的かを事前に見極めることが重要です。また、既存のCRMやIVRとのシステム連携の可否も事前確認が必須です。
社内教育とオペレーターとの連携体制構築
AI導入は単なる“置き換え”ではなく、“共存”の仕組みづくりが鍵です。そのためには、現場スタッフへの周知やトレーニングが欠かせません。「AIが仕事を奪う」という誤解を払拭し、むしろAIによって業務が楽になる、付加価値の高い対応に集中できるといった“ポジティブな変化”を浸透させる必要があります。また、AIがエスカレーションした問い合わせをスムーズに引き継げる体制整備も欠かせません。
ツール選定時のチェックポイント
AIツールを選ぶ際には、価格や機能だけでなく、以下のような観点も重要です。
- 自社業務との相性(チャット対応が多いのか、電話中心か)
- 学習能力と改善サイクルの柔軟性(AIが自動学習するのか、人手で調整が必要か)
- ベンダーのサポート体制(初期導入だけでなく運用サポートがあるか)
- セキュリティ・プライバシー対応(個人情報保護法やGDPRへの準拠)
安価なツールに飛びつくと、結局使いこなせず、現場に定着しないというケースも多く見られます。導入後の運用フェーズを見据えた選定が不可欠です。
コールセンターに導入されている主要AIツールとは?
AIと一口に言っても、用途や機能は多岐にわたります。コールセンターにおいては、チャットボット、音声認識、自然言語処理、会話型AIなどが主に活用されています。
ここでは、代表的なAIツールとその特徴・違いを整理してご紹介します。
ChatGPTなどの生成AIとチャットボットの違い
従来のチャットボットは、あらかじめ用意されたシナリオやFAQに沿って回答する“ルールベース型”が主流でした。一方、ChatGPTのような生成AIは、ユーザーの入力に対して柔軟に自然な文章を生成できるのが特長です。たとえば、曖昧な質問や想定外の問い合わせにも文脈を理解して対応できるため、より人間らしい対話が実現します。ただし、自由度が高い分、誤答や意図しない返答のリスクもあるため、業務用途では監視体制やガイドラインの設計が必要です。
音声ボットと対話AIの比較
音声ボットは、電話での問い合わせに自動音声で対応するAIです。たとえば「ご希望の内容をお話しください」と案内し、顧客の音声を認識して適切な回答や振り分けを行います。一方、対話AIはテキストベースでも音声でも使え、会話の流れを理解しながら複数ターンの対話が可能です。つまり、音声ボットが単発的な応答に強いのに対し、対話AIは複雑なやり取りや補足確認などを含むシナリオに適しています。用途に応じて使い分けることが重要です。
国産AI vs 海外製AIのメリット・デメリット
AIツールには、国内ベンダーが提供するものと、Google、Amazon、OpenAIなどの海外製があります。
国産AIのメリットは以下の通りです。
- 日本語の認識・解析精度が高い
- サポート対応が迅速
- 法規制(個人情報保護法など)に対する理解が深い
一方、海外製AIは
- 機能面・技術面での進化スピードが早い
- 高度な自然言語処理やクラウド連携に優れる
- グローバル展開している企業にとってはスケーラビリティが高い
選定にあたっては、自社のニーズや導入体制、対応言語、カスタマイズのしやすさなどを総合的に検討する必要があります。
実際のAI導入事例:成果を出している企業5選
AIの導入は、理論だけでなく実際の成功事例を通じてこそ、その効果や課題が具体的に理解できます。
ここでは、業界を代表する5社がコールセンター業務にAIを活用している事例を取り上げ、それぞれの導入目的・成果・学びを解説します。
1. NTT東日本:AIボイスボットによる問い合わせ対応
NTT東日本では、電報サービスや電話料金に関する問い合わせに対し、AIボイスボットを導入。従来は有人で対応していた問い合わせをAIが代替し対応を強化しました。問い合わせ内容を音声認識で把握し、自動で適切な回答を行うため、顧客満足度の向上と業務負担の軽減の両立に成功しています。
引用:
あなたの電話対応業務を生成AIが代行!電話業務の効率化・高度化を実現!~生成AIによる新しいIVRのかたち~
ボイスボットを有効活用する秘訣CX向上の設計図を描く
2. ソフトバンク:有人×AIチャットのハイブリッド型運用
ソフトバンクは、契約内容の確認や料金プラン変更などにAIチャットボットを活用。一次対応をAIが担い、複雑な問い合わせは有人チャットへとスムーズにエスカレーションするハイブリッド運用を採用しています。これにより、対応スピードの向上と、オペレーターのストレス軽減を実現しました。
引用:
日本マイクロソフトとの共同開発により、生成AIでコールセンター業務の自動化を加速
~お客さまの待ち時間の短縮と対応の均質化により、顧客満足度向上を目指す~
月間30万件のチャットボット入力!ソフトバンクとりらいあが目指す理想のチャットボットとは
3. 楽天:AIによる通話内容の自動テキスト化と品質分析
楽天グループでは、通話内容をAIがリアルタイムでテキスト化し、応対品質の自動分析を行っています。たとえば「謝罪が抜けている」「話が長すぎる」など、定量的なデータをもとに改善指導ができるため、SV(スーパーバイザー)の負担が軽減。品質維持と教育効率の両面で大きな成果をあげています。
引用:
楽天コネクト Storm
4. 三井住友銀行:AIによるFAQ応答+感情分析
三井住友銀行では、AIを活用したFAQチャットボットと、音声通話における感情分析ツールを導入。顧客の声のトーンや語調をAIが分析し、「不満」「怒り」などの感情を検出。早期にSVへ通知される仕組みにより、クレームの長期化や炎上を未然に防ぐ効果を発揮しています。
引用:
対話型 AI 自動応答システムの活用について
【事例多数】AIでコールセンター分析|効率化と顧客満足度を両立
5. JAL(日本航空):AIチャットで航空券変更に即対応
JAL(日本航空)では、コロナ禍以降に問い合わせが急増した航空券変更・キャンセル手続きの一部にAIチャットを導入。お客様の予約情報と連携しながら、会話形式で柔軟に対応できる点が特長です。対応時間の短縮と、有人窓口への負荷軽減に大きく貢献しています。旅行業界でもAIの有用性が広く認識され始めた事例です。
引用:
JAL、回答範囲カバー率90%のAIチャットボットを育てた好事例 ~コロナ禍や日々の変化にタイムリーに対応する「チャット自動応答サービス」~
今後の業界トレンドとAIの進化予測
AI技術は日々進化を遂げており、コールセンターにおける活用範囲も今後ますます広がっていくことが予想されます。
ここでは、特に注目される進化トレンドと、それがコールセンター運営に与える影響について考察します。
感情分析AIの普及とCX向上への期待
今後注目されるのが、音声やテキストから顧客の感情を読み取る「感情分析AI」です。声のトーンや話すスピード、文脈などを解析し、「怒っている」「困っている」「納得していない」といった心理状態をリアルタイムで検出する技術が進化しています。これにより、オペレーターが適切なタイミングでトーンを調整したり、SVが介入する判断を下せるようになり、CX(顧客体験)の向上につながります。
AIによる自動提案・ナレッジ支援の進化
生成AIの導入により、オペレーターが応対中にAIから「次にすべき対応」や「使えるマニュアル文言」がリアルタイムで提案される機能が急速に実用化されています。たとえば、「このお客様にはこのプランをおすすめできます」といった営業支援や、「このフレーズを使うと共感を得られます」といった応対ガイドの提供です。AIがナレッジベースとして“裏で支える存在”から、“その場で支援する存在”へと進化しつつあります。
離職率の低下に向けたAI支援の可能性
コールセンター業界では、オペレーターの離職率の高さが長年の課題となっています。原因の多くは、「業務負担の重さ」「クレーム対応の精神的ストレス」「マニュアルの多さによる混乱」などです。AIによる業務の自動化やナレッジ支援、ストレス状況の可視化などが進むことで、現場の負担を軽減し、職場環境の改善が期待されています。AIは、業務効率化だけでなく、“人が辞めない環境づくり”にも貢献できる存在になりつつあります。
よくある質問(FAQ)
コールセンターにAIを導入する際、よくある疑問や不安をまとめました。
導入を検討している企業の方や現場マネージャーの方にとって、判断材料となる情報をQ&A形式でご紹介します。
AIオペレーターとは何ですか?
AIオペレーターとは、チャットや音声を通じて自動で顧客対応を行うAIプログラムです。FAQの自動応答、本人確認、注文受付など、定型的な業務を人に代わって実行します。人間のように話しかけることができるため、利用者にストレスを感じさせにくいのが特徴です。
コールセンターが難しい理由は何ですか?
コールセンター業務が難しい理由は、顧客対応の多様さ・感情的な対応への配慮・短時間での正確な応答が求められることなどが挙げられます。また、応対品質を一定水準に保ち続けるには、高い教育・マネジメント力も必要です。こうした中でAIを適切に使うことで、業務負担を軽減する動きが進んでいます。
AIを導入するのにかかる費用はどのくらい?
導入費用はツールの種類・規模によって異なりますが、小規模のチャットボットなら月額数万円〜、音声ボットや高度な対話AIでは初期費用数百万円+月額費用というケースもあります。クラウド型なら初期投資を抑えやすく、段階的に始める企業も多いです。
中小企業でもAI導入は可能ですか?
はい、可能です。最近は中小企業向けの低コスト・低リスクなクラウド型AIソリューションも充実しています。問い合わせ数が少なくても、FAQや業務ナレッジの整備から始めることで、段階的な導入が可能です。
AIの導入でオペレーターの仕事はなくなりますか?
AIは“仕事を奪う”のではなく、“仕事の質を変える”存在です。定型業務はAIが代替し、オペレーターはより複雑で高度な対応や人間的なケアに集中できます。むしろ、オペレーターの役割は今後さらに重要になるといえるでしょう。
チャットボットとAIの違いは何ですか?
チャットボットは、あらかじめ用意されたシナリオに従って回答する“ルールベース型”が一般的ですが、AIは自然言語処理を用いて文脈を理解し、柔軟な応答が可能です。
最近では、生成AI(ChatGPTなど)を組み込んだ高度なチャットボットも登場しています。
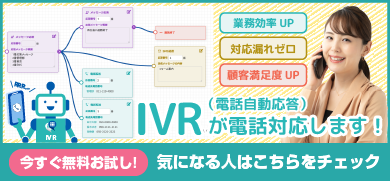
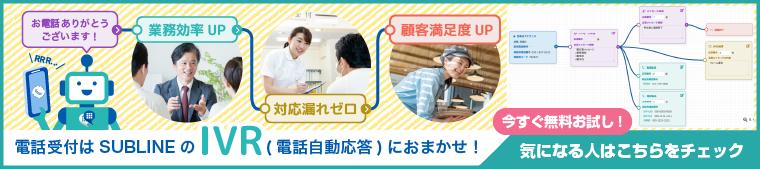
不要な電話対応にサヨナラ!
WEBで完結!無料お試しが可能です!
PROFILE

-
株式会社インターパーク/SUBLINEプロジェクトリーダー・マーケティング担当
中途で株式会社インターパークに入社。
仕事で使う050電話アプリSUBLINE-サブライン-のカスタマーサポート担当としてアサイン。
カスタマーサポートを経て、現在は事業計画の立案からマーケティング担当として事業の推進・実行までを担当。
過去、学生時代には2年間の海外留学を経験。