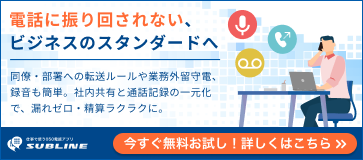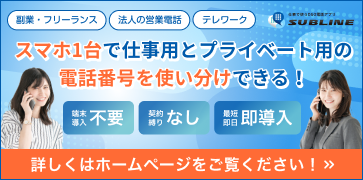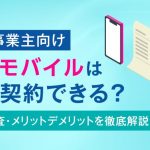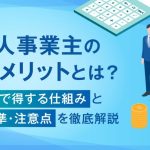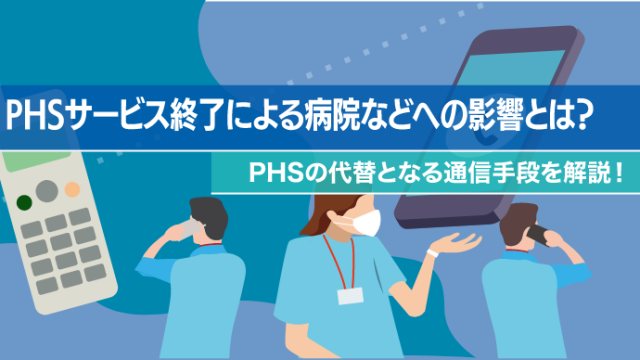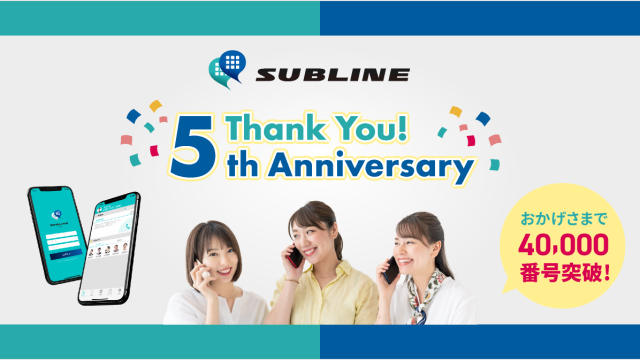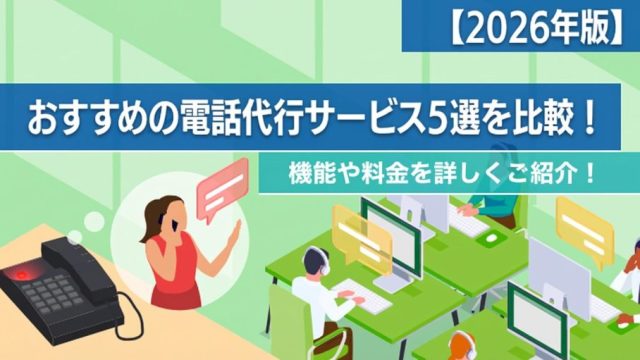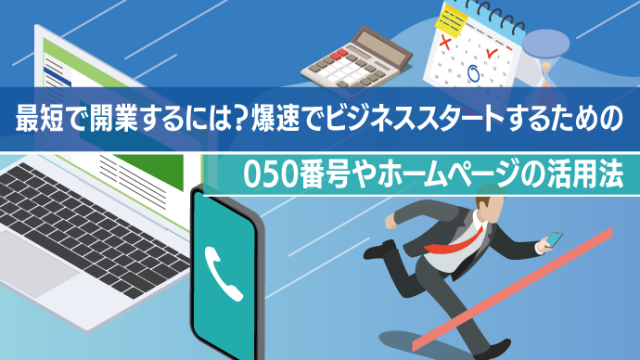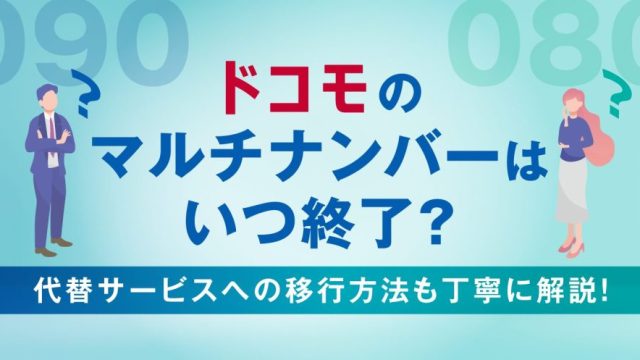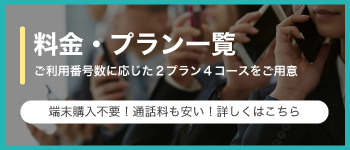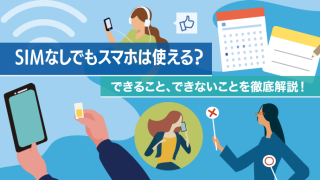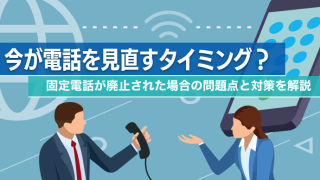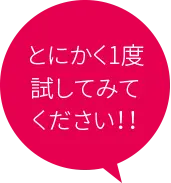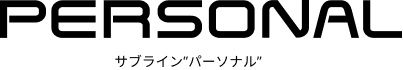スマホ対応クラウドPBXアプリを徹底比較。
本記事では、おすすめのアプリ5つの料金・機能・特徴を解説します。外出先で会社番号が使える仕組みも紹介します。
クラウドPBXアプリとは?仕組みと従来型PBXとの違い
クラウドPBXアプリは、従来のオフィス電話機能をインターネット経由で提供するサービスを、スマホやPCから利用できるようにしたものです。物理的なPBX(構内交換機)を設置せず、クラウド上で電話回線や内線機能を管理できるため、外出先や自宅からでも会社番号での発着信や内線通話が可能になります。
従来型PBXはオフィス内の専用機器で電話回線を制御するため、拠点ごとの機器設置や配線工事が必要でした。一方、クラウドPBXアプリはインターネット接続さえあれば利用できるため、導入コストや運用負担が大幅に軽減されます。
クラウドPBXの基本構造と通話の流れ
クラウドPBXは、電話番号や内線の管理をクラウドサーバーで行います。
通話の流れは以下の通りです。
- 発信者が番号をダイヤル
- 音声データがインターネット(VoIP)経由でクラウドPBXサーバーに送信
- サーバーが宛先を判断し、社内の内線や外線番号へ転送
- 相手が受信し、通話が成立
この仕組みにより、ユーザーは物理的なPBX機器がなくても、同様の機能を利用できます。
アプリで会社番号が使える理由
クラウドPBXアプリは、契約した会社番号(例:03番号、050番号など)をクラウド上で管理し、アプリ経由で発着信できるようにします。アプリを起動してログインすれば、スマホやPCが仮想的なビジネスフォンとなり、外出先でも会社番号を使った通話が可能になります。これにより、個人の携帯番号を相手に知らせず、統一された会社番号での対応が実現します。
利用可能な端末・OS(iOS / Android / PC)
多くのクラウドPBXアプリはiOS(iPhone / iPad)とAndroidスマホに対応しています。また、一部サービスではWindowsやMac用のソフトウェア版も提供され、デスクトップPCやノートPCからの利用も可能です。マルチデバイス対応により、在宅勤務中はPCから、外出中はスマホからといった使い分けができます。
利用シーン例(テレワーク・外回り・複数拠点)
クラウドPBXアプリは、以下のようなシーンで効果を発揮します。
- テレワーク:自宅からでも会社番号で発着信し、顧客対応を継続
- 外回り営業:訪問先から直接会社番号で電話し、信頼性を確保
- 複数拠点:拠点間を内線でつなぎ、通話料を削減
- 臨時拠点やイベント会場:物理工事不要で即日開設可能
この柔軟性が、従来型PBXにはない大きなメリットとなります。
クラウドPBXアプリを導入するメリット
クラウドPBXアプリは、業務の効率化やコスト削減を同時に実現できる点が大きな魅力です。特にスマホ対応アプリを導入すれば、外出先や在宅勤務中でも会社番号での通話が可能になり、働き方の柔軟性が格段に向上します。また、オフィスに依存しない通話環境は、災害時や緊急時の事業継続にも有効です。
外出先でも会社番号で発着信できる
クラウドPBXアプリを使えば、スマホやPCから会社番号で直接発信・着信が可能です。これにより、取引先や顧客には常に統一された番号が表示され、信頼性の確保と個人情報の保護を両立できます。営業担当者が外出中でもスムーズに顧客対応でき、折り返しの手間を減らせます。
内線通話・転送・保留がスマホで可能
従来は社内のビジネスフォンでしかできなかった内線通話や転送、保留といった機能が、クラウドPBXアプリならスマホでも使えます。例えば、外出先から社内スタッフへ内線で取り次ぎができ、顧客対応のスピードが向上します。
導入コストを抑えられる
物理的なPBX機器や専用電話機、配線工事が不要なため、初期費用を大幅に削減できます。また、従量課金型の料金プランを採用しているサービスも多く、必要な回線数や機能に応じて柔軟にコストを調整できます。
拠点追加や人員増加への柔軟対応
クラウドPBXアプリは、管理画面から簡単にユーザーや拠点を追加できます。これにより、新店舗の開設や一時的な人員増にも即時対応が可能です。物理機器の増設が不要なため、拡張性が高く、成長企業にも向いています。
クラウドPBXアプリの注意点・デメリット
クラウドPBXアプリは多くの利点がありますが、導入前に注意すべきポイントも存在します。特に通信環境や利用端末の性能、ユーザーの操作習熟度によっては、想定外の不便さを感じる場合があります。
ここでは、主なデメリットや注意点を解説します。
通信環境による音質の変化
クラウドPBXアプリはインターネット回線を利用するため、通信速度や安定性によって音質が変化します。Wi-Fiが不安定な場所やモバイル回線の電波が弱いエリアでは、音声が途切れたり遅延することがあります。業務利用では、安定した通信環境の確保が必須です。
スマホバッテリーの消費増加
常時アプリを起動して待ち受け状態にするため、スマホのバッテリー消費が増える傾向があります。長時間の外出や出張では、モバイルバッテリーを併用するなど、電源確保の工夫が必要です。
アプリ操作の慣れが必要
クラウドPBXアプリは機能が多く、内線や転送、履歴管理など操作方法を理解するまでに時間がかかる場合があります。特に従来のビジネスフォンに慣れているユーザーは、最初の操作トレーニングを実施することでスムーズな移行が可能になります。
インターネット障害時は利用不可
インターネット接続が前提のため、ネットワーク障害や停電時には利用できません。万一の際に備え、緊急連絡用の代替手段(携帯電話や別回線)を準備しておくことが重要です。
クラウドPBXアプリの選び方
クラウドPBXアプリはサービスごとに特徴や料金、サポート内容が異なります。導入後に「思っていたのと違った」という事態を避けるためにも、比較検討の際にはいくつかの重要ポイントを押さえておくことが大切です。
ここでは、選定時に確認すべき代表的な項目を解説します。
音質の安定性(コーデックや通信方式)
業務利用では音声品質が信頼性に直結します。選ぶ際には、利用する音声コーデックの種類(例:G.711、Opusなど)や、通信方式(SIP、WebRTCなど)を確認しましょう。音質を保証する「QoS(Quality of Service)」設定や、帯域確保ができるサービスであれば、より安定した通話が可能です。
セキュリティ機能(暗号化・端末認証)
顧客情報や社内の機密情報を扱うため、通話データやアカウント情報の保護は必須です。通話の暗号化(SRTPやTLS対応)や、登録端末を制限する端末認証機能が備わっているかを確認しましょう。不正アクセス防止のため、多要素認証を導入できるサービスもおすすめです。
他ツールとの連携(CRM・チャット)
クラウドPBXアプリによっては、CRMやSFA、チャットツール(Slack、Teamsなど)との連携機能があります。これにより、顧客情報の自動表示や通話履歴の自動保存が可能となり、業務効率が向上します。
料金体系とコスト感
サービスによっては、初期費用・月額基本料・内線数・通話料が異なります。社員数や利用形態に合わせて無駄のない料金体系を選びましょう。従量課金型や定額型など、料金モデルの違いも比較ポイントです。
無料トライアル・サポート体制
導入前に無料トライアルやデモ利用ができるサービスは、実際の音質や操作感を確かめられるため安心です。また、トラブル発生時に日本語で迅速に対応してくれるサポート体制も重要です。電話・メール・チャットなどサポートチャネルの多さも確認しましょう。
スマホ対応クラウドPBXアプリおすすめ5選
ここでは、スマホから会社番号での通話ができるクラウドPBXアプリを5つピックアップし、それぞれの特徴や強みを解説します。
法人から個人事業主、大規模コールセンターまで幅広く対応できるサービスを網羅しているので、自社の規模や目的に合わせて選定の参考にしてください。
トビラフォンCloud|迷惑電話対策に強みを持つPBX
トビラフォンCloudは、迷惑電話フィルタリングに強みを持つクラウドPBXアプリです。外部からの不審な電話を自動で判別・ブロックできるため、業務効率を妨げる迷惑着信を大幅に減らせます。
内線通話や転送など基本機能はもちろん、セキュリティ重視の企業や顧客対応品質を高めたい企業に向いています。
Good Line|低コストで使えるクラウドPBX
Good Lineは、コストを抑えながらクラウドPBXを導入したい中小企業におすすめのサービスです。
必要最低限の機能をシンプルな設計で提供しており、初めてクラウドPBXを導入する企業でも使いやすい仕様になっています。料金プランが明確で、ランニングコストを重視する企業に適しています。
MOT/TEL(モッテル)|ビジネスフォン代替に最適
MOT/TEL(モッテル)は、オフィスのビジネスフォン機能をそのままスマホやPCで利用できるクラウドPBXです。
特に既存の固定電話番号をそのまま移行したい場合に便利で、内線・転送・保留・録音など基本機能が揃っています。全国の中小企業で多く導入されており、サポート体制も充実しています。
03plus|03番号を取得できる個人事業主向け
03plusは、東京都内の市外局番「03」を取得できる珍しいクラウドPBXアプリです。
スマホ1台で発着信・留守電・FAX受信まで対応でき、低コストでの運用が可能です。名刺やWebサイトに03番号を掲載することで、信用力を高められます。
より簡単に導入するならIP電話アプリSUBLINE(サブライン)がおすすめ

SUBLINE(サブライン)は、お手持ちのスマホにアプリをインストールするだけで、プライベート番号の他にもう一つ、仕事用の050電話番号が持てるサービスです。
個人スマホにアプリを入れるだけなので、端末を新たに支給する必要がありません。
電話アプリの中でもSUBLINE(サブライン)は、クラウドPBXと同等の機能を備えつつ、導入や運用の負担を大幅に軽減できます。
スマホ1台で会社番号を利用でき、リモートワークや外出先でもビジネス通話が可能になるため、小規模事業から大企業まで幅広く活用できます。
詳しくは公式サイトをご覧ください。
公式サイト https://www.subline.jp/
クラウドPBXアプリ導入の流れ
クラウドPBXアプリは、従来型のビジネスフォンよりも導入がスムーズで、最短即日から利用開始できるサービスもあります。
ここでは、導入の一般的な流れを4つのステップに分けて解説します。
サービス契約とアカウント発行
まずは、利用したいクラウドPBXサービスを選び、契約を行います。契約が完了すると、管理者用のアカウントや各ユーザーの内線番号、ログイン情報が発行されます。利用する電話番号(新規取得または既存番号の移行)もこのタイミングで設定します。
アプリのインストールと初期設定
契約後、指定されたクラウドPBXアプリをスマホやPCにインストールします。その後、発行されたID・パスワードでログインし、内線番号や発着信設定を行います。音質設定や着信音、通知方法なども、この段階で自社の運用に合わせてカスタマイズします。
通話テストと利用開始
設定が完了したら、社内や外線へのテスト通話を行い、音質や着信動作に問題がないか確認します。内線通話、転送、保留などの機能も試し、想定通りに動作するかをチェックします。問題がなければ、正式に業務での利用を開始します。
安定した利用のための通信環境整備
クラウドPBXはインターネット回線が命綱です。Wi-Fiの電波強度や通信速度を事前に確認し、可能であれば有線接続や高速回線を利用することで、通話の安定性が向上します。また、モバイル利用の場合は、通信量やエリアカバー率の高いキャリアを選ぶことも重要です。
よくある質問
ここでは、クラウドPBXアプリを導入する際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。導入前の疑問解消や、比較検討時の参考にしてください。
クラウドPBXはいつサービス終了しますか?
クラウドPBXは比較的新しいサービス形態であり、現時点で主要サービスが終了する予定はありません。むしろ、リモートワークやDX推進の流れから利用者が増加しており、今後もサービス拡充が見込まれます。ただし、個別の事業者がサービス終了する可能性はゼロではないため、契約前にサポート体制や事業の安定性を確認しましょう。
クラウドPBXの欠点は何ですか?
最大の欠点は、インターネット環境に依存している点です。通信が不安定だと音声が途切れたり、通話できなくなる場合があります。また、スマホアプリの場合はバッテリー消費が増えることや、操作に慣れるまで時間がかかることもデメリットとして挙げられます。
PBXはiPhoneでも使えますか?
はい、多くのクラウドPBXアプリはiOS(iPhone・iPad)に対応しています。App Storeからアプリをダウンロードし、発行されたアカウント情報でログインすれば利用可能です。AndroidやPCと併用できるサービスも多く、マルチデバイス運用が可能です。
クラウドPBXの月額費用はいくらですか?
サービスや利用規模によって異なりますが、一般的には1ユーザーあたり月額1,000〜3,000円程度が目安です。通話料や追加機能の有無によって料金が変動するため、導入前に見積もりを取得し、総コストを確認することが重要です。
アプリを複数端末で使えますか?
多くのサービスでは、同一アカウントを複数端末で利用できます。ただし、同時着信や発信に制限がある場合もあるため、業務フローに合わせて設定や契約内容を確認しましょう。
社員ごとに内線番号を設定できますか?
はい、クラウドPBXでは社員ごとに内線番号を割り当てられます。これにより、拠点や部署をまたいだスムーズな内線通話が可能になります。管理画面から簡単に追加・変更ができるため、人事異動や新入社員の入社にも柔軟に対応できます。
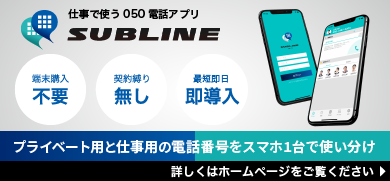

無料でお試しいただけます!
WEBで完結!最短即日で導入完了!
PROFILE

-
株式会社インターパーク/SUBLINEプロジェクトリーダー・マーケティング担当
中途で株式会社インターパークに入社。
仕事で使う050電話アプリSUBLINE-サブライン-のカスタマーサポート担当としてアサイン。
カスタマーサポートを経て、現在は事業計画の立案からマーケティング担当として事業の推進・実行までを担当。
過去、学生時代には2年間の海外留学を経験。