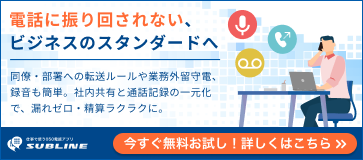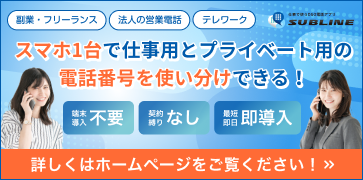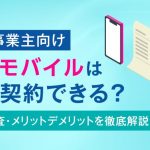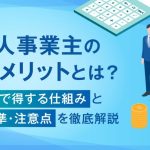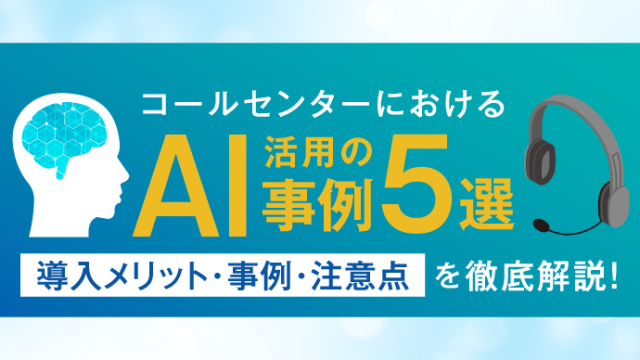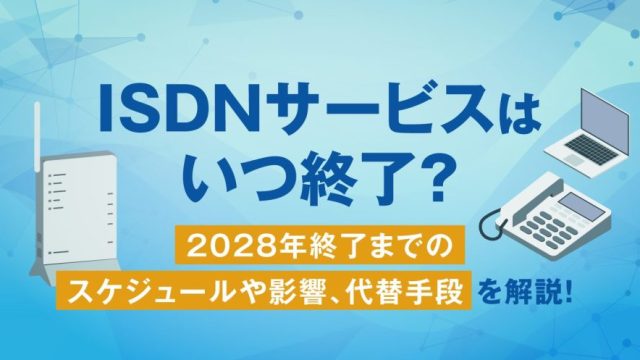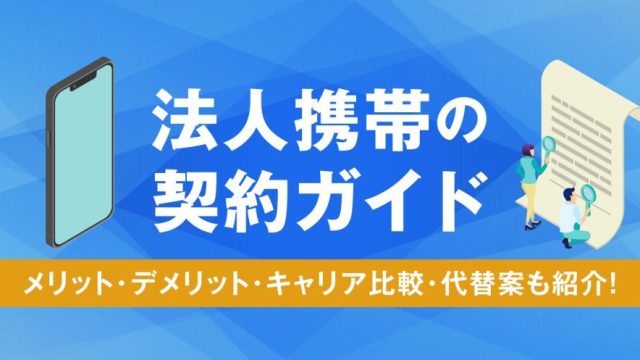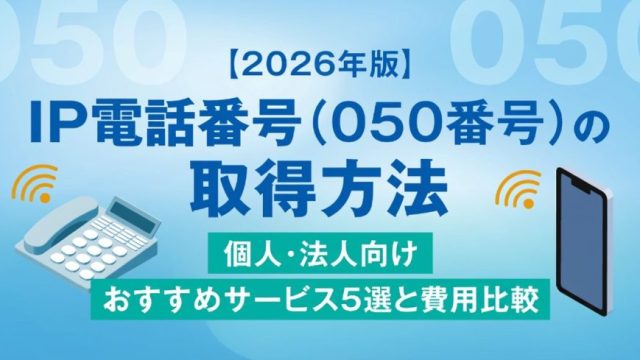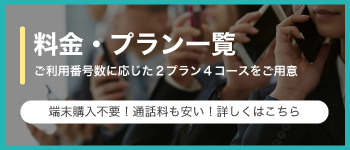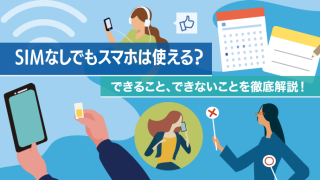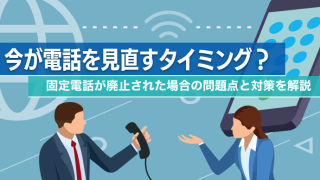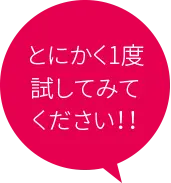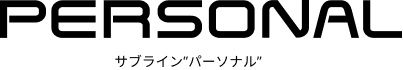クラウドPBX導入を検討中の方必見。
本記事では、通信品質や障害リスク、コスト面などのデメリットを具体的に解説し、回避策や導入の判断基準を提示します。さらに、代替案としておすすめのIP電話アプリもご紹介します。
クラウドPBXのデメリットを理解する重要性
クラウドPBXは、場所や端末を選ばずにビジネス電話を利用できる便利な仕組みですが、全ての企業や業務にとって万能なわけではありません。導入前にデメリットを把握していないと、運用開始後に予期せぬ不満やトラブルが発生し、結果的に業務効率やコスト面で損失を招く可能性があります。
ここでは、導入を検討するうえでなぜデメリットの理解が重要なのか、その理由を解説します。
なぜデメリットを把握する必要があるのか
新しいシステム導入では「便利さ」や「コスト削減」といったメリットに目が行きがちです。しかし、クラウドPBXの場合、通信品質の不安定さや障害時の通話停止リスク、既存機器との互換性の問題など、業務に直結する影響を与えるデメリットが存在します。これらを事前に把握しておくことで、対策を講じたり、自社の利用環境と適合するかどうかを判断でき、導入後の後悔を防ぐことができます。
導入前に確認すべき業務との相性
クラウドPBXが真価を発揮するのは、多拠点展開やリモートワークを積極的に取り入れている企業です。一方で、長時間の通話が多い業務や、アナログ機器を頻繁に使う業種では不便を感じる場合もあります。業務フロー、通話量、必要機能、既存機器の使用状況などを総合的に確認し、クラウドPBXが本当に自社の運用に適しているかを見極めることが重要です。
技術面・品質面のデメリット
クラウドPBXはインターネット回線を通じて通話を行うため、従来の固定電話とは異なる品質面でのリスクがあります。回線環境やネットワーク構成によっては、音声品質の低下や通話障害が発生しやすくなるため、導入前に十分な検討が必要です。
回線品質による音声遅延・ノイズの発生リスク
クラウドPBXは回線の安定性に依存するため、回線速度が遅い、または通信が混雑している状況では、音声が遅延したり、途切れたり、雑音が混じることがあります。特に、社内ネットワークに大量のデータ通信が発生している場合や、Wi-Fi環境が不安定な場合には、顕著に影響が出やすくなります。
停電・ネットワーク障害時に通話できない可能性
クラウドPBXはインターネット接続が途切れると利用できなくなります。停電や通信障害、ルーター故障などが発生すると、社内外との通話が一切できなくなるリスクがあり、業務停止につながる恐れがあります。災害時や緊急対応が必要な業務では、このリスクは特に大きな問題になります。
セキュリティリスクと不正利用対策の必要性
クラウドPBXはインターネット経由で通信を行うため、不正アクセスや盗聴、アカウント乗っ取りのリスクがあります。適切な暗号化やアクセス制限、二要素認証などのセキュリティ対策を講じなければ、情報漏洩や高額な不正通話料金の発生につながる可能性があります。
運用・機能面での制限
クラウドPBXは多機能で柔軟性が高い一方、既存の設備や業務形態によっては、従来の固定電話システムに比べて制限や不便さを感じることがあります。特に、アナログ機器の利用や特定の通話環境が必須な業種では、導入後に運用上の課題が浮き彫りになる場合があります。
既存アナログ機器やFAXとの非互換
クラウドPBXはIP電話回線を利用するため、従来型のFAX機やアナログ回線専用のビジネスフォンとは直接接続できない場合があります。FAXをどうしても利用する必要がある企業では、別回線の契約やFAXサーバーの導入など追加対応が必要になるため、コストや運用が複雑化する可能性があります。
コールセンターや長時間通話での品質不安
長時間の通話や高頻度の発着信を伴う業務では、クラウドPBX特有の通信遅延や音声品質の揺らぎが顕在化することがあります。特にコールセンターのように高い通話品質が求められる環境では、ネットワークや回線品質に万全の対策を施さないと、顧客満足度や業務効率の低下につながります。
緊急通報における位置情報の制約
クラウドPBXからの110番や119番への発信は、固定電話と違い発信元の正確な位置情報が自動的に伝わらない場合があります。そのため、緊急時には発信者が住所や位置情報を口頭で伝える必要があり、迅速な対応が求められる場面で不便となる可能性があります。
コスト・契約面の落とし穴
クラウドPBXは初期費用が安く、導入しやすいという印象がありますが、契約内容や利用年数によっては予想外のコスト負担が発生する場合があります。また、料金体系や契約条件を十分に確認しないと、解約や機能追加の際に不利益を被る可能性があります。
長期利用で割高になる可能性
クラウドPBXは月額課金制が一般的で、初期導入費用は抑えられるものの、5年・10年と利用を続けると総コストがオンプレミス型PBXより高くなるケースがあります。特に、利用人数や拠点数が多い企業では、ユーザー単位の課金体系が長期的な費用増につながりやすいため、事前のシミュレーションが重要です。
最低契約期間や違約金の存在
クラウドPBXサービスには最低利用期間が設定されている場合があり、その期間内に解約すると違約金が発生することがあります。業務形態の変化や規模縮小で利用をやめたくなった場合でも、契約条件によっては予想以上のコストを負担することになります。契約前に必ず期間や解約条件を確認することが必要です。
オプション追加によるコスト膨張
通話録音、IVR(自動音声応答)、通話転送などの機能はオプションとして提供される場合が多く、必要に応じて追加していくと月額料金が大幅に増えることがあります。導入前に必要機能を洗い出し、基本料金に含まれる範囲とオプション料金を明確にしておくことが、予算超過を防ぐポイントです。
導入・社内運用の課題
クラウドPBXは機能面で優れていても、社内の運用体制やスキルによっては導入後に思わぬ負担が発生することがあります。システムの使いこなしや管理体制が整っていないと、効率化どころか業務停滞の原因になる場合もあります。
社内のITスキル不足による運用負担
クラウドPBXの設定や運用には、ネットワーク構成や端末設定に関する基本的な知識が求められます。社内にITスキルを持つ人材がいない場合、初期設定やトラブル対応のたびに外部業者へ依頼することになり、コストや対応時間の面で負担が増える可能性があります。
通話フローや番号体系の見直し負担
従来の固定電話システムからクラウドPBXへ移行する際には、内線番号や転送ルール、着信フローの見直しが必要になることがあります。これに伴い、社内マニュアルの修正や社員への周知・教育が必要になり、移行初期は業務の混乱が生じるリスクがあります。
サポート対応のスピード・品質への不安
クラウドPBXのサポート体制はサービス提供会社によって異なり、電話やチャットでの即時対応が難しい場合もあります。障害や不具合が発生した際に迅速に解決できないと、業務停止が長引き、顧客対応にも悪影響を与える可能性があります。サポートの品質や受付時間は契約前に確認しておくことが重要です。
デメリットを最小限にする方法
クラウドPBXには一定のデメリットがありますが、適切な準備や運用方法を取れば、多くの課題は軽減できます。
ここでは、導入前後に実践すべき具体的な対策を紹介します。
高品質な回線と冗長化の導入
音声品質や安定性の向上には、十分な帯域幅を確保できる回線選びが重要です。専用回線や光回線を利用するほか、ルーターやスイッチの性能も見直しましょう。また、回線冗長化(メイン回線が故障した際に自動で予備回線に切り替える仕組み)を導入することで、障害時の通話断絶リスクを大幅に減らせます。
サポート重視のサービス選定
導入時や障害発生時の安心感を確保するには、サポート体制の充実したサービスを選ぶことが重要です。電話・チャット・メールなど複数のサポート窓口があり、かつ即時対応が可能な会社を選ぶことで、業務中断の時間を最小限にできます。契約前にサポート品質を確認するため、試験運用や問い合わせテストを行うのも有効です。
社内トレーニングと運用ルール整備
クラウドPBXをスムーズに運用するには、社員全員が基本的な使い方やトラブル対処方法を理解している必要があります。導入時にマニュアルを整備し、定期的な研修を実施することで、運用ミスやサポート依存を減らせます。着信・転送ルールなどの運用ルールを明確化することも、混乱防止に効果的です。
クラウドPBXのメリットと比較バランス
クラウドPBXにはデメリットだけでなく、多くの企業にとって魅力的なメリットも存在します。重要なのは、メリットとデメリットのバランスを理解し、自社にとってプラスになるかどうかを判断することです。
ここでは、代表的なメリットと、それがデメリットを上回るケースについて整理します。
初期費用の低さと柔軟な拡張性
クラウドPBXはオンプレミス型と異なり、専用機器の購入や大規模工事が不要なため、初期費用を大幅に抑えることができます。また、利用人数や拠点数が増減しても、ライセンスの追加・削除で簡単に対応できるため、事業の成長や縮小に柔軟に対応可能です。
リモートワークや多拠点運営との相性
インターネット経由で利用できるため、在宅勤務や出張先、支店など場所を問わず同じ内線番号で通話できます。これにより、全国・海外に拠点を持つ企業や、フルリモートを導入している企業でも、社内外との円滑なコミュニケーションを維持できます。
デメリットを上回るケースの条件
クラウドPBXのデメリットは、回線品質やセキュリティ対策、社内教育である程度カバー可能です。特に、通話品質に影響しにくい業務形態や、全国規模で拠点を持つ企業、リモート主体の組織では、コスト面・利便性のメリットがデメリットを大きく上回るケースが多く見られます。
他の選択肢 電話アプリという選び方
クラウドPBXの導入が難しい、またはデメリットが大きいと感じる場合、電話アプリという別の選択肢も検討できます。スマホやPCにインストールして使える電話アプリは、初期費用や機器の制約が少なく、導入までのハードルが低い点が魅力です。
クラウドPBXとの違いと特徴
クラウドPBXは企業全体の電話システムをインターネット経由で構築しますが、電話アプリはよりシンプルで、個別の端末に直接導入して利用します。そのため、システム構築や大規模な設定が不要で、少人数のチームや新規事業立ち上げ時にもスピーディーに運用を開始できます。
導入が簡単な電話アプリのメリット
電話アプリは、契約から利用開始までが短く、数日以内で運用を始められることが多いのが特徴です。また、既存のスマホやPCをそのまま利用できるため、専用端末の購入や工事が不要です。さらに、アプリによっては通話録音や転送など、クラウドPBXに近い機能を備えているものもあり、コストを抑えつつ必要な機能を確保できます。
スマホで使えるビジネス電話 050電話アプリSUBLINE(サブライン)

SUBLINE(サブライン)は、お手持ちのスマホにアプリをインストールするだけで、プライベート番号の他にもう一つ、仕事用の050電話番号が持てるサービスです。
個人スマホにアプリを入れるだけなので、端末を新たに用意する必要がありません。
電話アプリの中でもSUBLINE(サブライン)は、クラウドPBXと同等の機能を備えつつ、導入や運用の負担を大幅に軽減できます。
スマホ1台で会社番号を利用でき、リモートワークや外出先でもビジネス通話が可能になるため、小規模事業から大企業まで幅広く活用できます。
詳しくは SUBLINE公式サイト をご覧ください。
導入判断のためのチェックリスト
クラウドPBXや電話アプリを導入する際は、事前にいくつかのポイントを確認しておくことで、導入後のトラブルや無駄なコストを防げます。
以下のチェック項目を参考に、自社の状況に最適な選択肢を見極めましょう。
自社の回線環境
現在のインターネット回線が、安定した音声通信に耐えられる品質かを確認します。帯域幅や遅延、障害発生率などを把握し、必要であれば回線の増強を検討しましょう。
業務フローとの適合度
既存の通話フローや顧客対応プロセスが、クラウドPBXや電話アプリの仕様に適しているかを確認します。通話量、内線・外線の使用比率、録音や転送の必要性なども判断材料となります。
コストシミュレーション
初期費用・月額費用・オプション料金・契約期間中の総コストを試算します。短期的な安さだけでなく、長期的な費用負担も含めて比較することが重要です。
サポート体制の重要度
トラブル発生時にどの程度迅速かつ的確に対応してもらえるかを確認します。対応チャネル(電話・メール・チャット)や受付時間、サポート実績もチェックポイントです。
他サービスとの比較結果
クラウドPBX、電話アプリ(サブラインなど)、オンプレミスPBXなど、複数の選択肢を比較検討します。機能・コスト・運用負担のバランスを考え、自社に最も合ったサービスを選びましょう。
よくある質問
クラウドPBXの欠点は何ですか?
主な欠点は、インターネット回線品質に依存するため音声遅延やノイズが発生する可能性があること、停電や回線障害時に利用できなくなること、既存のアナログ機器との互換性が低いことです。また、長期利用でコストが高くなるケースや、サポート対応のスピードに不満が出る場合もあります。
クラウドPBXはいつ終了しますか?
クラウドPBX自体は、現状終了予定があるサービスではありません。ただし、提供事業者によってはサービスの仕様変更や終了が発表される場合がありますので、契約時に利用規約やサポート方針を確認し、長期利用に耐えられるかを見極めることが重要です。
クラウドPBXの課題は?
課題としては、安定した通信環境の確保、セキュリティ対策の徹底、社内での運用ルールの整備が挙げられます。また、通話品質が業務品質に直結する業種では、クラウドPBXの特性を十分に理解して運用体制を整える必要があります。
クラウドPBXで緊急電話はかけられますか?
可能ですが、固定電話のように自動で正確な位置情報が通知されない場合があります。そのため、緊急通報時には発信者が住所や状況を正確に伝える必要があります。業務上、緊急通報の利用頻度が高い場合は、この制約を考慮しておくべきです。
クラウドPBXと電話アプリはどう違いますか?
クラウドPBXは企業全体の電話システムを構築し、内線・外線・IVRなど多機能を統合的に管理できます。一方、電話アプリは個別の端末に導入して利用する形式で、設定や運用負担が軽く、少人数や短期利用に向いています。
SUBLINEはクラウドPBXの代わりになるのですか?
はい。SUBLINEはクラウドPBX並みの通話録音・IVR(自動音声応答)・転送機能を備えており、スマホ1台で会社番号を利用できます。導入コストが低く、専用機器や工事が不要なため、小規模から中規模の企業や、スピーディーな運用開始を求めるケースに特に適しています。
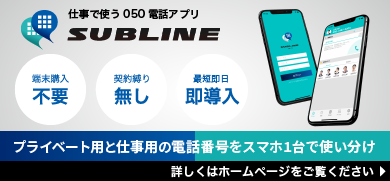

無料でお試しいただけます!
WEBで完結!最短即日で導入完了!
PROFILE

-
株式会社インターパーク/SUBLINEプロジェクトリーダー・マーケティング担当
中途で株式会社インターパークに入社。
仕事で使う050電話アプリSUBLINE-サブライン-のカスタマーサポート担当としてアサイン。
カスタマーサポートを経て、現在は事業計画の立案からマーケティング担当として事業の推進・実行までを担当。
過去、学生時代には2年間の海外留学を経験。