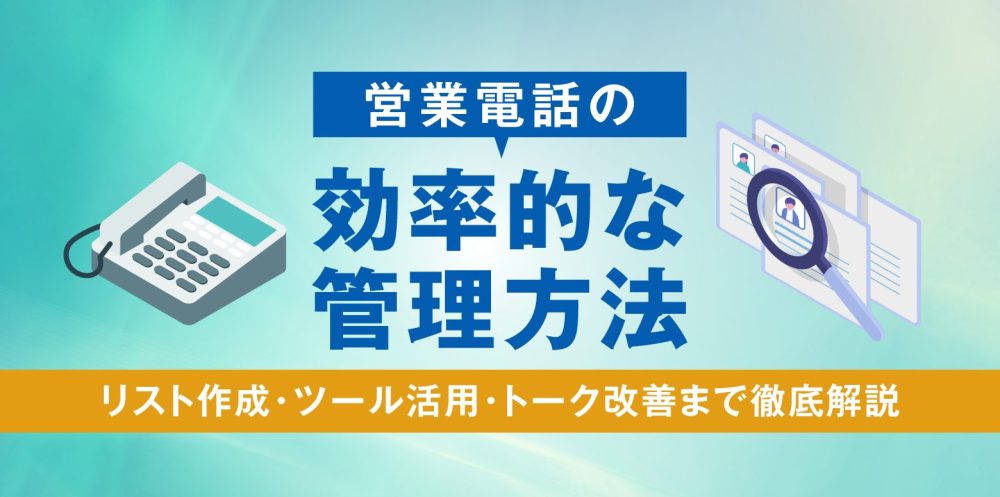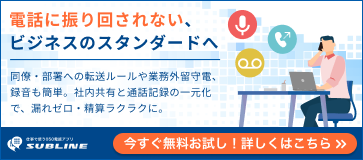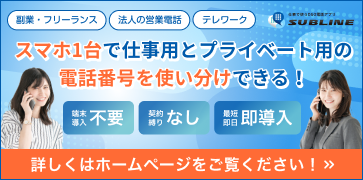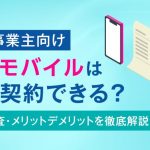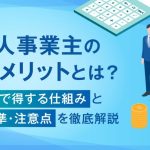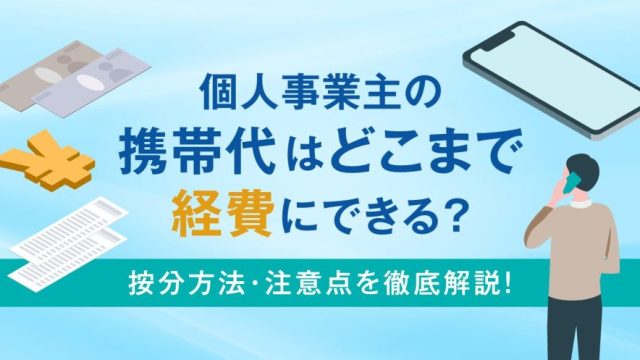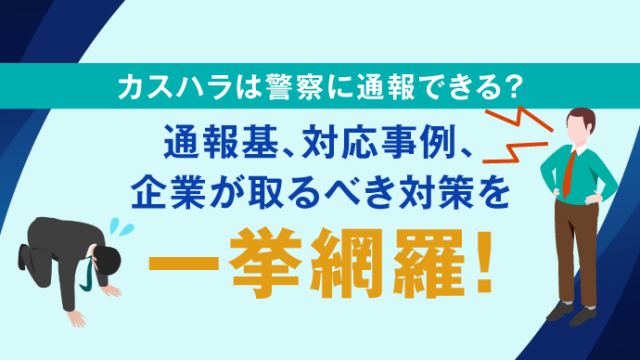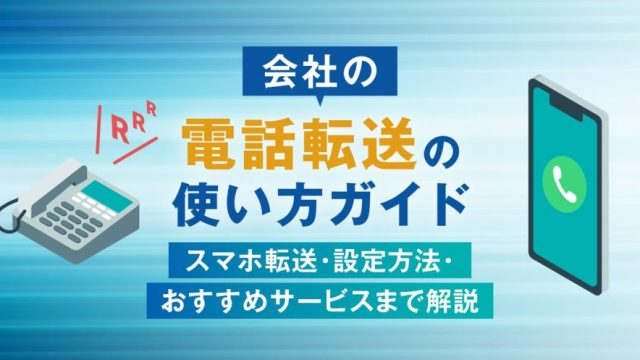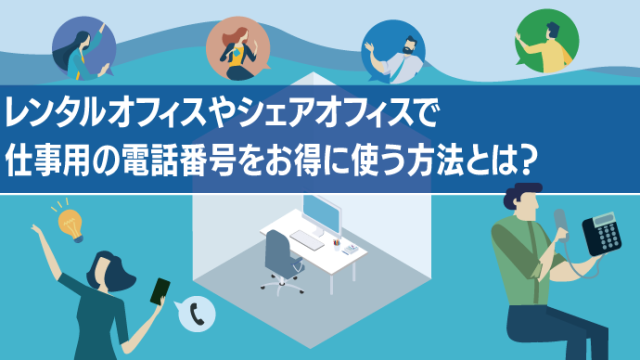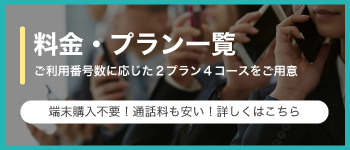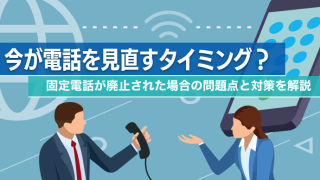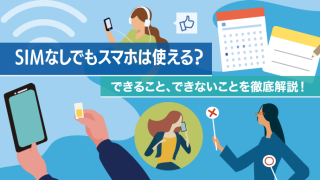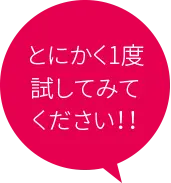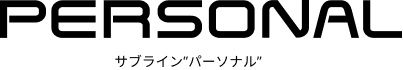本記事では、営業電話の成果を高める管理方法を解説。リスト作成のコツ、ExcelやCRM・CTIを使った管理、トーク改善や心理的ハードルの克服まで網羅。
携帯2台持ちのデメリットと、業務効率を高める「サブライン」の活用法もご紹介いたします。
営業電話を管理する重要性とは
営業電話は単純に「数をかければ良い」というものではありません。成果につなげるためには、架電対象の選定や進捗状況の把握、次のアクションをどう設定するかといった「管理」が不可欠です。管理が不十分だと、重複して同じ相手に電話してしまったり、フォローが漏れて信頼を損なうこともあります。効率的に営業活動を行うためには、管理方法を体系的に整える必要があります。
なぜ“管理”が成果に直結するのか
営業電話の成果は「的確な相手に、適切なタイミングで連絡できるか」にかかっています。リストが散乱している状態では、アプローチすべき見込み客を逃したり、既存顧客への対応が後手に回るリスクが高まります。管理を徹底することで、優先順位付けが明確になり、効率よく成約につながる行動を積み上げることが可能になります。
効率と品質を両立させる仕組み作り
単に「量」を追うだけでは、クオリティの低いアプローチが増え、結果的に成約率が下がってしまいます。逆に品質だけに偏ると、架電数が減って機会損失を招きます。そのため、効率と品質のバランスを意識した仕組みが必要です。例えば、リストを定期的に精査し、優先度を設定したうえでトークスクリプトを改善していくことで、量を確保しながら精度の高い提案ができるようになります。
架電リストの作り方と活用法
営業電話の成果を高めるには、まず「誰に電話をするのか」を明確にすることが重要です。無作為に電話をかけても効率が悪く、担当者に迷惑をかけてしまうリスクもあります。リストを戦略的に作成し、段階的に活用することで、成約率の高いアプローチが可能になります。
既存顧客情報をベースにする方法
もっとも効果的なのは、既存の顧客情報や取引履歴を活用したリスト作成です。すでに接点がある相手は信頼関係を築きやすく、クロスセルやアップセルにつながる可能性が高まります。過去の購買データや問い合わせ履歴を整理し、架電優先度を設定することで、効率的なアプローチが実現します。
SNSやアクセス解析を活用した新規開拓
自社のWebサイトやSNSを訪問しているユーザーは、すでに関心を持っている見込み客です。アクセス解析で行動データを収集し、どのページを閲覧しているかを把握すれば、興味関心の高い層を抽出できます。さらに、SNSのフォロワーやコメントを残したユーザーも、潜在的なリスト候補として有効です。
有料リスト購入を検討する際の注意点
新規顧客開拓では、有料の営業リストを購入する選択肢もあります。しかし、精度の低いリストは不在や無効番号が多く、時間を浪費してしまうリスクがあります。購入する際は、業種・エリア・企業規模など条件を細かく指定できる業者を選び、定期的にリストを更新することが重要です。また、リスト依存に偏らず、自社での情報収集と併用することが望まれます。
管理方法の選択肢:Excel vs 専用ツール
営業電話の管理方法には、大きく分けて「Excelなどの汎用ツールを活用する方法」と「CRM・SFA・CTIなどの専用システムを導入する方法」があります。自社の規模や予算、営業体制によって最適な手段は異なります。
ここではそれぞれの特徴を整理し、どのように使い分けるべきかを解説します。
Excelを活用したシンプルな管理術
Excelは初期コストがかからず、自由度が高いのが大きな利点です。顧客リストや架電状況、次回アクション予定などを一元的に記録でき、営業担当者自身が使いやすい形にカスタマイズできます。ただし、データ量が増えると管理が煩雑になりやすく、複数人での共有やリアルタイム更新には限界があります。小規模チームやスタートアップには有効ですが、規模拡大に伴い専用ツールへの移行を検討すべきです。
CRM・SFAとの連携で実現できる効率化
CRM(顧客関係管理)やSFA(営業支援システム)を導入すると、顧客情報を自動的に整理し、営業活動全体を見える化できます。例えば、メール配信履歴やWebサイトの閲覧履歴を統合管理することで、架電前に相手の関心度を把握可能になります。また、チーム内で進捗状況を共有できるため、フォロー漏れの防止や効率的な分担が実現します。中長期的に営業組織を成長させるなら、CRMやSFAは欠かせない仕組みです。
CTI導入による架電履歴・録音の一元管理
CTI(Computer Telephony Integration)を導入すると、電話システムと顧客管理が連動し、架電履歴や通話録音を自動で保存できます。これにより、担当者が変わっても過去の対応内容を即座に把握でき、顧客満足度の向上につながります。さらに、通話内容を分析することで、トーク改善や教育にも活用可能です。特にコールセンターや電話営業を主力とする企業では、CTIは業務効率と品質を両立させる強力なツールとなります。
営業電話の目的と進め方
営業電話は単なるアポイント獲得の手段ではなく、相手との信頼関係を構築し、将来的な取引へつなげる重要なプロセスです。無計画に電話をかけるのではなく、目的を明確にし、戦略的に進めることで成果につながります。
ここでは、電話をかける前に準備しておくべきことから、実際の進め方までを解説します。
架電前に押さえておくべき情報収集
営業電話を成功させるには、相手の企業や担当者について事前に情報を集めておくことが欠かせません。企業の公式サイトやSNS、プレスリリースから最新の事業動向を把握すれば、会話のきっかけや提案内容に具体性を持たせることができます。また、過去の取引履歴や問い合わせ履歴があれば、それらを整理して「相手にとって有益な話題」を準備することが大切です。
目的を明確化してアプローチするコツ
営業電話は「ただ話す」ことが目的ではなく、「アポイントを取る」「資料送付の承諾を得る」「次のステップにつなげる」など、具体的なゴールを持つことが重要です。目的を明確にすれば、会話の流れが整理され、不要な情報を並べ立てることなく相手にとって価値のある提案ができます。
信頼を得るための話し方と流れ作り
電話は顔が見えない分、第一声から相手に安心感を与える必要があります。明るく落ち着いたトーンで名乗り、相手の時間を尊重する姿勢を示すことで、拒否されにくい空気を作れます。そのうえで、簡潔に要点を伝え、相手の反応を聞きながら柔軟に話を進めることが信頼獲得の第一歩です。最後に「次回の約束」や「資料送付」など具体的な行動に結びつけると、成果につながりやすくなります。
電話トーク最適化のポイント
営業電話は第一印象と会話の流れで結果が大きく変わります。限られた時間で相手に好感を持たれ、こちらの提案を前向きに受け止めてもらうためには、トークの最適化が不可欠です。ここでは、トークの切り出し方から要点の伝え方、断られたときの対応までを具体的に解説します。
第一声で印象を左右する言葉選び
電話営業において、最初の数秒で相手の印象が決まると言われます。名前と会社名をはっきり伝えるのはもちろん、「今お時間よろしいでしょうか?」といった配慮の一言があるだけで、相手の反応は大きく変わります。相手が忙しそうであれば「1分だけお話させてください」と具体的に時間を提示することで、会話が始まりやすくなります。
短時間で要点を伝えるトーク設計
営業電話は長々と説明するよりも、相手が知りたい情報を端的に伝えることが大切です。自社のサービスや商品の特徴を「3つのポイント」に絞り、シンプルに話すことで理解が進みやすくなります。また、相手に質問を投げかけ、対話の形にすることで、一方的な売り込みではなく「会話」を成立させることができます。
断られたときの切り返しテクニック
断られることは営業電話では日常茶飯事です。しかし、すぐに引き下がるのではなく「また別の機会にご連絡差し上げてもよろしいでしょうか?」と次につなげる工夫が有効です。また、「今は必要ない」と言われた場合でも、「どのような点で不要と感じられますか?」と丁寧に理由を伺うことで、今後の改善につながる貴重な情報を得られます。切り返しは強引さを出さず、誠実さを持って対応することが信頼を積み重ねる鍵となります。
営業電話の心理的ハードルを減らす工夫
営業電話は「断られるのが当たり前」という現実があるため、担当者にとって心理的な負担が大きくなりがちです。そのストレスを軽減できる仕組みを整えることで、長期的に安定したパフォーマンスを維持することが可能になります。
ここでは、精神的なハードルを下げるための具体的な方法を紹介します。
断られることを前提にしたメンタル調整法
営業電話では、10件中9件は断られるケースも珍しくありません。これを「失敗」と捉えると気持ちが折れてしまいますが、「断られるのが前提」と考えるだけで精神的な負担は軽くなります。また、断られた経験を記録し、「次はどう改善できるか」を振り返ることで、失敗を学びに変えることができます。ポジティブな自己対話を習慣化することも、気持ちを前向きに保つ有効な手段です。
成功率より行動量を評価する仕組みづくり
営業電話は短期的な成果だけで評価すると、担当者が疲弊してしまいます。そこで、成果だけでなく「行動量」に焦点を当てた評価基準を導入することが有効です。例えば「1日30件架電する」「1週間で100件フォローする」といった数値目標を設定すれば、担当者は成果に一喜一憂せず、安定したリズムで業務に取り組めます。行動を評価する仕組みは、モチベーション維持とスキル向上の両面で効果を発揮します。
長期的なマネジメントの視点
営業電話は短期的な成果を追うだけでは持続しません。チーム全体のスキルを高め、長期的に安定した成果を出すためには、マネジメントの視点が欠かせます。成果至上主義からプロセス重視へのシフト、そして教育体制の整備が、営業活動の質を大きく左右します。
成果主義からプロセス重視へのシフト
営業電話は「成果=アポイント数」だけで評価されがちですが、それでは担当者のモチベーションが低下しやすく、短期的な成果に偏ってしまいます。マネジメント層は「架電数」「ヒアリングの質」「トーク改善の取り組み」など、プロセスそのものを評価基準に含めることで、担当者が安心して取り組める環境を整える必要があります。プロセスを重視する姿勢は、長期的に見込み客との関係性を深め、結果的に高い成約率につながります。
チーム全体のスキルを底上げする教育法
個々の担当者に任せきりにするのではなく、チーム全体のスキルを底上げする仕組みが重要です。具体的には、通話録音を活用したロールプレイング研修や、成功事例・失敗事例の共有会を定期的に行うと効果的です。また、マニュアルやトークスクリプトを常にアップデートし、誰でも一定の成果を出せる体制を整えることで、組織としての安定感が増します。教育と改善の循環を仕組み化することで、チームの成長が持続します。
営業マンが携帯を2台持ちするデメリット
営業マンが「仕事用とプライベート用に携帯を2台持つ」ことは一般的ですが、実際には多くのデメリットを抱えています。コストや管理面での負担が大きく、業務効率の低下やストレスにつながるケースも少なくありません。
ここでは、2台持ちの主な問題点を整理します。
コスト負担の増加
携帯電話を2台契約すると、端末代金や通信費が単純に2倍になります。特に通話量が多い営業担当者の場合、毎月の固定費が膨らみ、会社にとっても個人にとっても大きな負担になります。長期的に見れば、通信コストだけで数十万円の差が生まれることも珍しくありません。
管理の手間や紛失リスク
2台の携帯を常に持ち歩くのは手間がかかります。どちらに着信があったかを確認する必要があり、連絡の見落としにつながるリスクも高まります。また、外出先で紛失や盗難に遭った場合のリスクも倍増します。管理が煩雑になるほど、営業活動に集中できなくなるのが現実です。
私生活との境界があいまいになる問題
仕事用と個人用で携帯を分けても、結局は2台とも持ち歩く必要があるため、私生活と仕事の切り替えが難しくなります。休日や夜間に仕事用の電話が鳴ることで、オンオフの境界が曖昧になり、プライベートの時間が侵食されるケースもあります。こうした負担は、長期的にモチベーションや働き方の質に影響を与えます。
050電話アプリSUBLINE(サブライン)で解決する営業電話の課題
営業電話の効率を高めたい一方で、携帯を2台持つことによるコストや管理の負担に悩む担当者は少なくありません。そんな課題を解決できるのが、スマホ1台で複数の番号を使い分けられるSUBLUNE(サブライン)です。
050電話アプリSUBLINE(サブライン)とは?

SUBLINE(サブライン)は、お手持ちのスマホにアプリをインストールするだけで、プライベート番号の他にもう一つ、仕事用の050電話番号が持てるサービスです。
個人スマホにアプリを入れるだけなので、端末を新たに支給する必要がありません。
営業先に外出する人、社用携帯を持つのがメンドウな人、社用携帯のコストを削減したい人に最適です。
SUBLINEは1名から100名以上まで、企業規模問わず導入でき、営業活動の効率化とプライベートの保護を同時に実現できます。
詳しくは SUBLINE公式サイト をご覧ください。
よくある質問
営業電話で言ってはいけないNGワードは?
相手の立場を否定したり、強引に契約を迫るような言葉はNGです。例えば「絶対に得です」「今契約しないと損します」といった押しつけがましい表現は不信感を招きます。代わりに「ご興味があれば詳しくご案内いたします」といった柔らかい言い回しが有効です。
営業電話を受けた側の対策方法は?
企業側での対策としては、迷惑電話対策サービスの導入や、事前に「電話は受け付けていません」と告知しておく方法があります。また、必要な場合は担当部署に直接つなぐ体制を作ることで、無駄な対応を減らすことができます。
営業電話は1日に何件くらいが目安?
業種やリストの質によって異なりますが、一般的には1日30~50件が現実的な目安です。単純に件数を増やすよりも、リストの精度を高め、1件ごとの会話の質を重視する方が成果につながります。
営業電話の最初の一言はどうすればいい?
第一声は「会社名+名前」を明るく、はっきり伝えることが基本です。その上で「今お時間よろしいでしょうか?」と相手を気遣う一言を添えることで、会話がスムーズに始まりやすくなります。
ExcelとCRM、どちらで管理すべき?
少人数での営業活動ならExcelでも十分対応できますが、チーム規模が大きくなるとCRMの導入が効率的です。CRMは顧客情報の共有や進捗管理に優れており、長期的な営業体制の強化につながります。
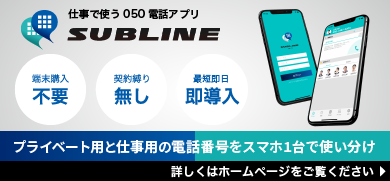

無料でお試しいただけます!
WEBで完結!最短即日で導入完了!
PROFILE

-
株式会社インターパーク/SUBLINEプロジェクトリーダー・マーケティング担当
中途で株式会社インターパークに入社。
仕事で使う050電話アプリSUBLINE-サブライン-のカスタマーサポート担当としてアサイン。
カスタマーサポートを経て、現在は事業計画の立案からマーケティング担当として事業の推進・実行までを担当。
過去、学生時代には2年間の海外留学を経験。