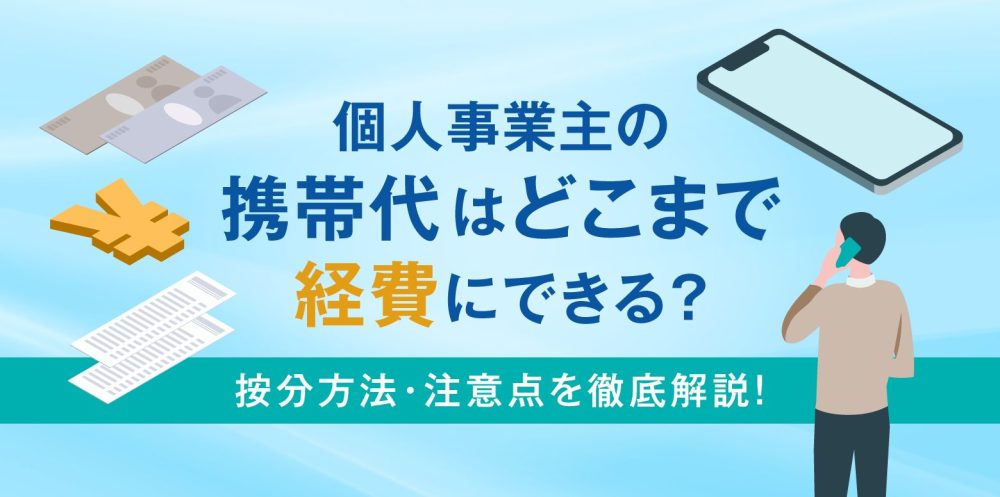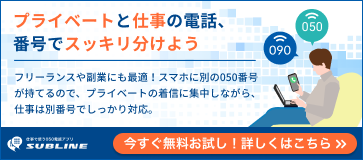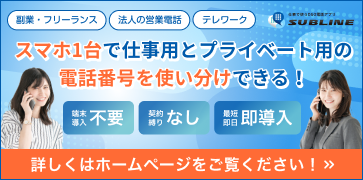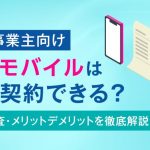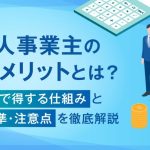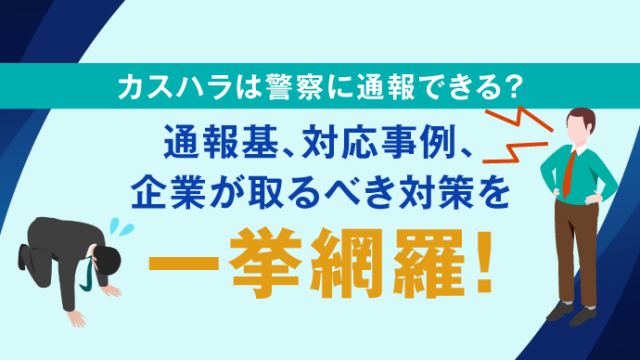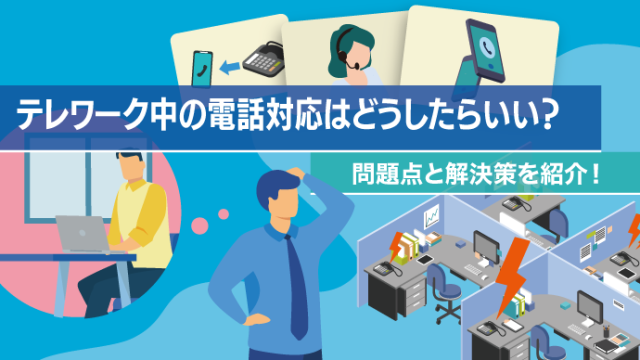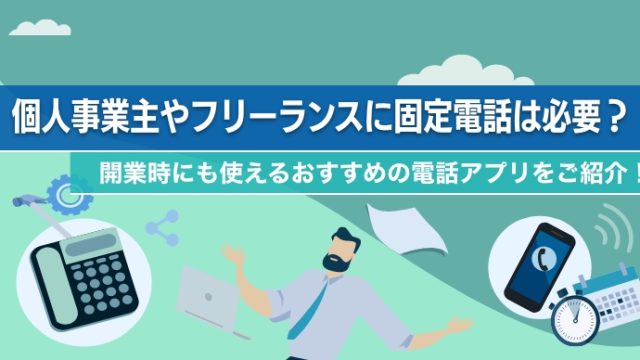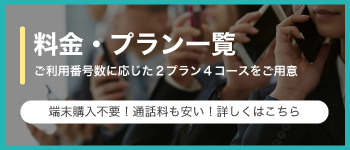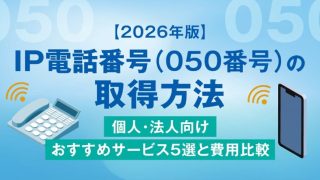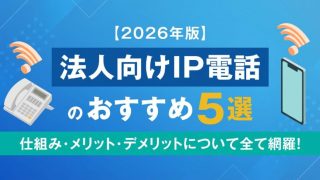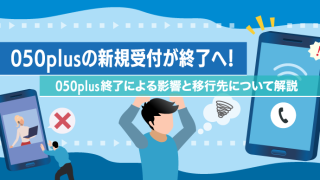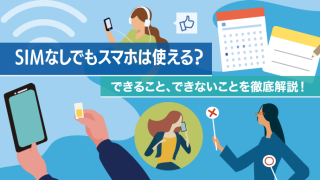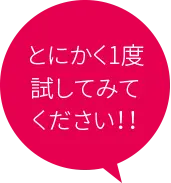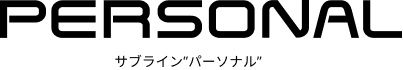個人事業主の携帯代は「仕事に使った分」だけ経費計上が可能です。
本記事では、経費にできる条件、按分方法、証拠の残し方、税務署対策、さらにIP電話サービスを活用したスマートな経費管理術まで詳しく紹介します。
経費になるもの・ならないものの具体例
携帯代の中でも、どこまでを経費にできるのかは明確に区別する必要があります。業務に直接関係のある支出は経費になりますが、プライベートな利用分は経費にできません。
ここでは、具体的に「経費になるもの」「ならないもの」、そして判断が難しい“グレーゾーン支出”への対処法を紹介します。
経費になる支出|業務関連の通話・通信費
携帯代のうち、以下のような事業に直接関係する支出は経費に計上できます。
- ・取引先や顧客との通話、メール、LINE連絡
- ・業務用アプリ(チャットツール、クラウドサービス)の通信費
- ・SNS運用、ネット広告出稿などのオンライン業務
- ・商談、営業、サポート対応にかかる通話時間や通信データ量
- ・スマホの業務利用に伴う追加オプション費用(例:通話かけ放題プランなど)
これらは「事業を継続、拡大するために必要な通信費」とみなされるため、経費として認められやすいです。
経費にならない支出|私的利用・家族利用など
一方で、次のようなプライベート目的の支出は経費にはできません。
- ・家族や友人との通話、SNS、メール
- ・プライベートな買い物、趣味サイトの通信
- ・家族で共有しているスマホの通信料(業務利用が明確でない場合)
- ・携帯ゲーム、動画視聴など業務と無関係なデータ通信
こうした支出を経費として計上してしまうと、税務署から否認されるリスクがあります。特に家族共用の携帯やデータ通信料は、業務利用分を合理的に按分しておくことが大切です。
グレーゾーン支出を安全に処理するコツ
「完全に仕事とは言い切れないが、一定の業務利用がある」…そんな曖昧なケースでは、証拠を残しながら慎重に処理するのが鉄則です。例としてあげると、SNS運用や情報収集目的の通信費であれば業務に関連する投稿や作業履歴を記録する、カフェなどでのWi-Fi利用なら打ち合わせや執筆作業など業務内容をメモに残す、家族共有スマホの利用なら業務時間・通話履歴を確認し、使用割合を明記するといった具合です。
税務署が確認するのは「その支出が事業の成果に結びついているかどうか」。少しでも迷う場合は、経費として計上する前に使用目的を明確に言語化しておくと安全です。
携帯代を経費に計上する実務ポイント
携帯代を経費にできると分かっても、「実際にはどう処理すればいいのか」「確定申告でどこに入力するのか」が分からないという人も多いのではないでしょうか。そんな人のために、確定申告での入力方法や仕訳の仕方、按分の考え方、そして書類の保存方法まで、実務的なポイントを具体的に説明します。
確定申告での入力先は「通信費」?それとも「雑費」?
携帯料金は、一般的に「通信費」として仕訳します。ただし、携帯代以外の通信関連費(Wi-Fi・インターネット・クラウドサービスなど)と一緒にまとめて記録することも可能です。
もし携帯を業務でたまにしか使わない、もしくは利用目的がはっきりしない場合は、「雑費」として処理しても問題ありません。ただし、毎月発生するような支出や通信業務の比重が高い場合は、税務上「通信費」で統一するほうが信頼性が高くなります。
クラウド会計ソフト(freeeやマネーフォワードなど)を使う場合も、「通信費」カテゴリーを選べば自動で勘定科目が整理されます。
クレジットカードや口座引き落としの場合の仕訳方法
携帯料金をクレジットカードや銀行口座から自動引き落としにしている人も多いでしょう。仕訳の基本形は次の通りです。
例:携帯料金10,000円のうち、業務利用が70%の場合
通信費 7,000円 / 普通預金 10,000円
事業主貸 3,000円
このように、仕事用の割合だけを経費(通信費)として処理し、プライベート分は「事業主貸」として計上します。
クレジットカードを使っている場合も同様に、支払時点で按分して記録します。クラウド会計ソフトを利用している場合は、カード明細を自動取り込みした後に、業務割合を設定すれば自動仕訳が可能です。
按分率の決め方とメモの残し方
携帯代を按分するときに重要なのは、「合理的な根拠をもって割合を決める」ことです。以下のような考え方で按分率を設定しましょう。
- ・業務時間の割合(例:1日のうち仕事8時間、私用2時間 → 80%経費)
- ・通話履歴や通信量(仕事用の通話件数・データ通信量の比率)
- ・仕事専用アプリの使用状況(LINE WORKS、Slackなど)
按分率を決めたら、
- ・「携帯利用のうち業務利用7割」とメモを残す
- ・年に1回は利用実態を見直す
- ・根拠となるスクリーンショットや明細を保存
これらをセットで残しておくと、税務署からの指摘にも安心です。
明細の保存期間と整理術
携帯料金の明細・請求書は、原則7年間の保存義務があります(白色申告は5年間)。書類を紙で保管するのは手間がかかるため、電子データで整理するのがおすすめです。
効率的な保存方法は、「携帯会社のWeb明細を毎月PDFでダウンロード」、「クレジットカード明細を自動取得してクラウド保存」、「freee・マネーフォワードなどの会計ソフトと連携して仕訳を自動化」となります。
また、税務署が確認する際は「経費としての整合性」を重視するため、請求書の宛名・支払方法・金額が一致しているかも定期的にチェックしておきましょう。
税務署に否認されないための注意点
携帯代の経費計上は、比較的認められやすい項目ですが、使い方や記録の残し方によっては「私用との区別が不明確」と判断され、否認されることもあります。特に通信費は、税務署がチェックする頻度の高い勘定科目のひとつ。
ここでは、税務調査で疑われないために押さえておきたいポイントを整理します。
経費率が高すぎると疑われるケース
携帯代を全額経費にしている人や、通信費の割合が他の個人事業主に比べて明らかに高い場合は、税務署が注目します。例えば、年商500万円の事業で通信費が年間60万円を超えると、「業務実態と合っているか?」と確認される可能性があります。
特に注意すべきは、携帯代を毎月全額経費にしている、家族と共用のスマホを100%経費扱いにしている、通信費が売上に対して10%を超えるといったケースです。
こうした場合は、按分の根拠をメモや明細で残しておくと安心です。
税務調査で聞かれやすいポイント
税務調査では、担当者が次のような点を重点的に確認します。
- ・携帯は誰が使っているのか?(本人以外の使用がないか)
- ・どのくらい仕事で使っているのか?(使用割合の根拠)
- ・請求書、明細書の名義は誰になっているか?
- ・事業内容と通信費のバランスは取れているか?
これらに答えられるよう、按分メモ・通話履歴・明細データを残しておくと、スムーズに説明できます。「いつ・誰と・どんな目的で」電話を使っているのか、ざっくりでも整理しておくと信頼度が上がります。
明細・通話履歴をどう説明すれば安心か
税務署の担当者は、経費を否認することが目的ではなく、「事業と私用の線引きが明確か」を確認しています。そのため、次のように説明できれば問題ありません。
- ・通話・通信履歴を確認して、業務利用の割合を定期的に見直している
- ・請求書や明細を電子保存してすぐ提出できる状態にしている
- ・家族と共用の場合は、自分の利用部分をメモで明確化している
「業務のために合理的に使っている」という説明ができれば、ほとんどのケースで経費として認められます。また、経費率に不安がある場合は、税理士に一度チェックしてもらうのも有効です。
携帯経費をスマートに分けるならIP電話サービス!
携帯代を経費として扱う上で、「仕事とプライベートの線引きが難しい」「按分の管理が面倒」という悩みを持つ人は多いです。そんなときに便利なのが、IP電話サービスです。スマホ1台でプライベート用と仕事用の番号を切り分けられるため、通話履歴や通信費をスッキリ管理できます。
ここでは仕組みとメリット、そしておすすめのIP電話サービス「SUBLINE(サブライン)」について解説します。
IP電話サービスとは?仕組みと特徴
IP電話とは、インターネット回線を使って通話する電話サービスのことです。従来の携帯や固定電話のように回線を通すのではなく、アプリを使って通話を行う仕組みです。
主に以下のような特徴があります。
- ・インターネット接続さえあれば、どこでも発着信が可能
- ・050番号を使って通話できる(携帯・固定電話どちらにも発信可能)
- ・通話料が安く、コスト削減効果が高い
- ・端末を複数持たなくても、1台のスマホで番号を分けて運用できる
つまり、「仕事用」と「プライベート用」の通話を1台で切り分けられるため、携帯経費を合理的に管理できるのが最大の強みです。
携帯のIP電話サービスのメリットは経費計上だけではない!
IP電話は経費処理を楽にするだけでなく、ビジネスの効率化にも役立ちます。主なメリットを列挙しておくので、参考にしてください。
- 通話履歴や発信記録を自動で残せる → 顧客対応の記録が簡単
- 複数番号を使い分けられる → 業務内容や担当者ごとに番号を分離できる
- どこでも発着信が可能 → 外出先・在宅ワークでも柔軟に対応
- 通信費を削減できる → 通話料は携帯キャリアよりも安価
- 信頼性アップ → プライベート番号を伝えずに仕事用番号を公開できる
こうした点から、税務面のメリットだけでなく、業務の効率化・セキュリティの向上にもつながるツールとして注目されています。
SUBLINE(サブライン)で携帯経費をもっとスマートに

SUBLINE(サブライン)は、お手持ちのスマホにアプリをインストールするだけで、プライベート番号の他にもう一つ、仕事用の050電話番号が持てるサービスです。
個人のスマホにアプリを入れるだけなので、端末を新たに用意する必要がありません。
低コストかつ短期間で仕事用電話を導入したい方に最適です。
また、1名から100名以上まで、企業規模問わず導入しやすいのも特徴です。
詳しくは公式サイトをご覧ください。
公式サイト https://www.subline.jp/
携帯代を経費にする前にやっておくと良いこと
携帯代を経費にするのは簡単に見えて、実は「事前準備」がものを言います。特に税務署が重視するのは、「業務利用を合理的に説明できる状態にあるかどうか」。
ここでは、経費処理のトラブルを防ぐために、個人事業主があらかじめやっておくべき実務的なポイントを紹介します。
仕事用の番号・アプリを導入する
もっとも効果的なのは、仕事用の連絡手段を明確に分けることです。プライベートとの混在を防げる上、経費按分の根拠がはっきりします。
代表的な方法としては2つあり、1つ目が「仕事用のSIMやサブ回線を契約する」。2つ目が「IP電話アプリ(例:SUBLINE)を導入する」です。
後者のほうがコストを抑えつつ、発信・着信履歴を自動で分けられるため、経費処理も楽になります。
名義と契約プランを見直す
携帯の契約名義が家族名義のままになっている場合は、事業主本人名義に変更しておくのが理想です。また、仕事での利用が多いなら、業務向けの通話プラン(かけ放題・データ容量大きめ)への切り替えも検討しましょう。
名義・契約プランを整えておくことで、請求書・明細書を「事業の証拠資料」として堂々と提示できるようになります。
経費比率をメモしておく
携帯代を経費にするときの按分率(業務利用の割合)は、自己申告でも認められます。ただし、「どうしてその割合にしたのか」を説明できるようにしておくことが重要です。
やる事として、仕事での通話時間を集計して割合を算出したり、月ごとに業務利用の傾向をメモする、使用割合を年度ごとに見直しなどといった記録を残しておけば、税務署に聞かれてもスムーズに説明できます。
クラウド会計ソフトとの連携設定
経費の入力や仕訳を効率化したいなら、クラウド会計ソフトとの連携が欠かせません。freeeやマネーフォワードを利用すれば、以下のような処理が自動化できます。
- ・クレジットカードや銀行口座の明細を自動取得
- ・携帯会社の請求データを連携
- ・支出内容を「通信費」として自動仕訳
- ・領収書データを電子保存(電子帳簿保存法にも対応)
日常的に記録を自動化しておくことで、確定申告のときに「まとめ作業」が一気にラクになります。
よくある質問
携帯代を経費にしたい個人事業主からは、共通した疑問が数多く寄せられます。
ここでは、実際に多くの人がつまずくポイントを整理し、専門家の視点でわかりやすく解説します。
個人事業主は携帯代を経費にできますか?
はい、携帯を仕事に使っている分は経費にできます。取引先との通話や業務連絡、広告運用など、事業に関連した通信はすべて「通信費」として計上可能です。ただし、プライベート利用が混ざる場合は、業務利用の割合(按分率)を設定しておくことが大切です。
経費としてスマホは10万円までですか?
スマホ本体の購入費は、10万円未満なら一括で経費計上できます。10万円以上の場合は、「減価償却資産」として数年にわたり分割して経費処理する必要があります。また、通信費(毎月の携帯代)はこの制限の対象外で、使用割合に応じて毎月経費にできます。
iPhoneは経費で落とせますか?
もちろん可能です。iPhoneを業務で使用しているなら、その購入費は経費になります。
ただし、プライベートでも使用している場合は、業務利用割合で按分します。また、アクセサリ(ケースやケーブルなど)は「消耗品費」、アプリやクラウドサービスの利用料は「通信費」や「ソフトウェア使用料」として計上します。
白色申告でも通信費は経費になる?
はい、白色申告でも通信費は経費にできます。青色申告と違って帳簿の形式は簡易ですが、領収書や明細を保管しておく義務は同じです。仕事で使った分が明確に分かるように、請求書や通話明細を保存しておくと安心です。
携帯を家族名義で使っている場合は?
家族名義でも、実際に事業で使っていれば経費計上は可能です。ただし、支払いを事業主がしていること、業務利用があることを説明できるようにしておく必要があります。家族と共有している場合は、業務で使った割合を按分し、明細を根拠として残しておくのが安全です。
IP電話を使うとどのくらい節約できる?
IP電話サービスは、通話料が携帯キャリアの約半分に抑えられるとされています。さらに、スマホ1台で複数番号を使い分けられるため、プライベートと仕事を分離しやすく、経費按分も明確になります。初期費用0円・契約縛りなしで導入できるため、携帯経費を効率化したい個人事業主には現実的な選択肢です。
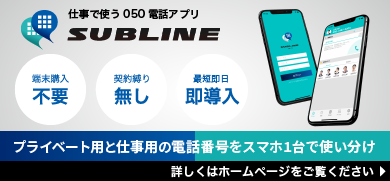

無料でお試しいただけます!
WEBで完結!最短即日で導入完了!
監修者

-
株式会社インターパーク/SUBLINEプロジェクトリーダー・マーケティング担当
中途で株式会社インターパークに入社。
仕事で使う050電話アプリSUBLINE-サブライン-のカスタマーサポート担当としてアサイン。
カスタマーサポートを経て、現在は事業計画の立案からマーケティング担当として事業の推進・実行までを担当。
過去、学生時代には2年間の海外留学を経験。