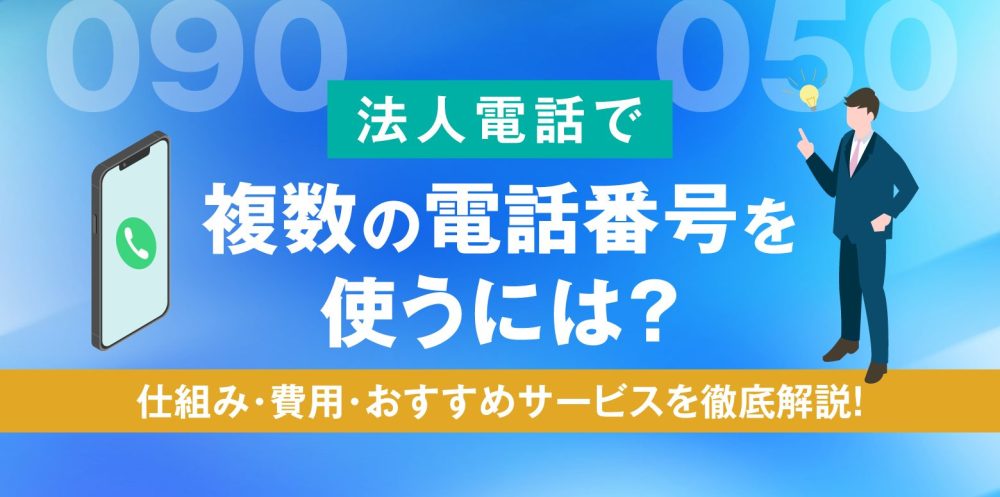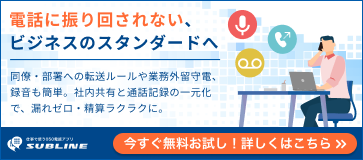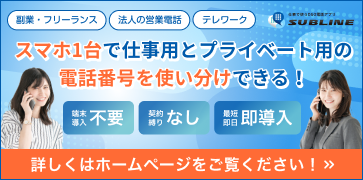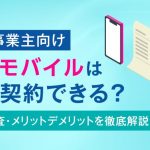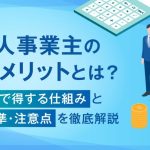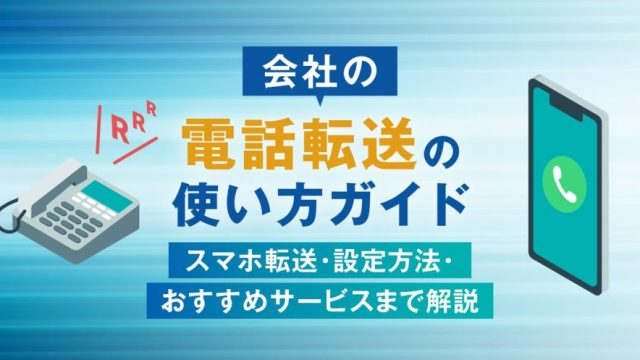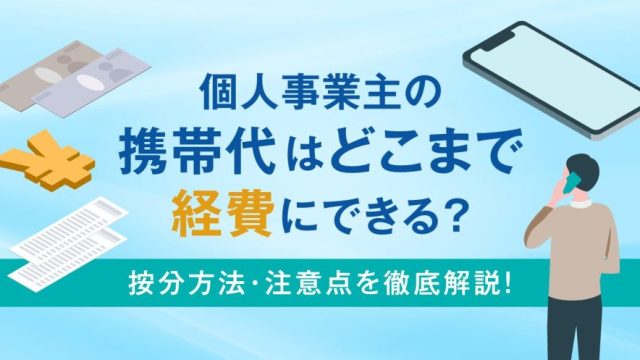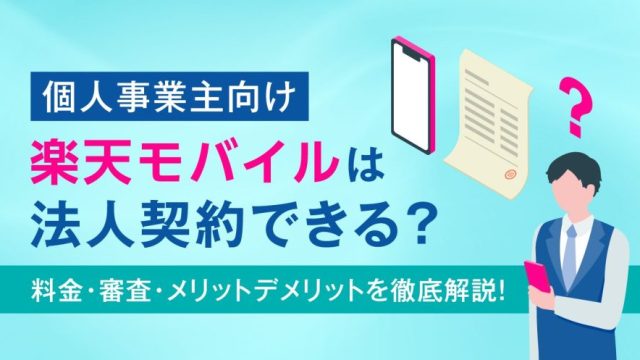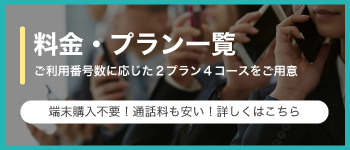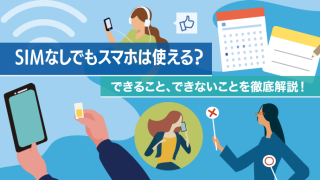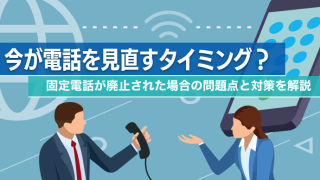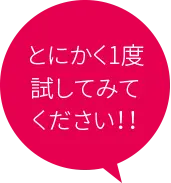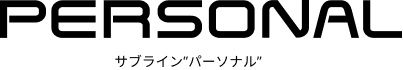本記事では、法人電話で複数の電話番号を利用する方法をわかりやすく解説します。
ダイヤルインや代表組の違い、回線ごとの制限、費用相場、注意点、そしておすすめのIP電話サービスもご紹介します。
法人電話で複数番号を使うには?基本のしくみを解説
法人電話において「複数の電話番号を持ちたい」と考える企業は少なくありません。例えば、電話とFAXを番号で分けたい、部署ごとに直通番号を設けたい、代表番号と採用専用番号を区別したいなど、利用シーンはさまざまです。こうしたニーズに応えるため、法人向けの電話サービスには「1回線で複数の番号を持つ仕組み」が用意されています。
1つの法人契約で複数番号を持てる?
法人電話では、1つの契約回線に対して追加番号を設定できるサービスがあります。これにより、代表番号とは別に営業直通番号やFAX専用番号を用意でき、契約回線を増やさずに複数の番号を使い分けることが可能です。この仕組みを利用すれば、オフィスの規模を問わず効率的な電話環境を構築できます。
電話とFAXを番号で分ける方法
法人利用では「電話番号は1つで足りる」とは限りません。FAXを導入している企業では、代表番号にFAXが届いてしまうと業務に支障をきたすケースもあります。そのため、電話とFAXを別番号で運用するのが一般的です。番号を分けることで、FAX専用番号に送られたデータは確実にFAX機に届き、電話対応に割り込みが入ることもありません。
部署別に電話番号を使い分けるメリット
営業、サポート、採用など部署ごとに番号を分けることで、顧客や取引先がスムーズに担当部署へつながります。代表番号に一度受けた電話を内線で転送する手間が減り、応対スピードの向上にもつながります。また、各番号ごとに着信履歴や通話量を把握できるため、業務改善や人員配置の見直しにも役立ちます。結果として「電話対応の効率化」と「顧客満足度の向上」の両立が可能になります。
複数番号の使い方は2通り!「ダイヤルイン」と「代表組」を比較
法人電話で複数の番号を使う方法には、大きく分けて「ダイヤルイン」と「代表組」の2つがあります。どちらも法人利用に広く採用されている仕組みですが、目的や使い方に違いがあるため、導入前にしっかりと理解しておくことが大切です。
ダイヤルインとは?複数番号をもつ基本機能
ダイヤルインとは、1本の回線に複数の電話番号を割り当てる仕組みです。これにより、代表番号のほかに直通番号やFAX番号を追加でき、1回線で効率よく複数番号を利用できます。たとえば、営業担当者に直通番号を割り当てれば、代表番号を経由せず直接担当者にかけてもらえるため、顧客対応のスピードが格段に上がります。
代表組とは?回線をシェアして効率運用
代表組(代表番号組み合わせ)とは、複数の回線を1つの代表番号にまとめて運用する方法です。代表番号に電話がかかると、空いている回線に自動で接続されるため「話し中」でつながらないといった事態を防ぐことができます。特に着信数が多い企業やコールセンターでは、代表組による運用が業務効率化に大きく貢献します。
どちらを選ぶべき?シーン別おすすめ活用法
ダイヤルインと代表組は、それぞれ向いているシーンが異なります。
- ダイヤルインがおすすめ:部署や担当者ごとに直通番号を割り当てたい場合、FAXと電話を分けたい場合。
- 代表組がおすすめ:着信数が多く、常に電話が混み合う状況を避けたい場合。
中規模以上のオフィスでは「ダイヤルインで番号を分け、代表組で同時着信をさばく」といった組み合わせも有効です。用途に応じて最適な方法を選ぶことで、電話対応の効率と顧客満足度を同時に高められます。
回線の種類と同時通話の制限を知っておこう
複数番号を活用する際に忘れてはならないのが「同時通話数(チャネル数)」の制限です。どれだけ番号を増やしても、回線の種類によって同時に使える通話数が異なるため、業務に必要な規模に応じた選択が欠かせません。
ここではアナログ、ISDN、光回線・クラウドPBXの特徴を整理していきます。
アナログ回線の特徴と制限
アナログ回線は昔ながらの固定電話サービスで、1回線につき1番号、同時通話は1通話のみが基本です。複数番号を持つこと自体は可能ですが、同時に複数人が通話することはできません。そのため、小規模事務所や利用頻度の低いオフィス向きであり、大量の着信が発生する環境では不向きです。
ISDN回線で使えるチャネル数とは?
ISDN回線は1回線で2チャネルを持ち、同時に2通話まで可能です。アナログ回線に比べて柔軟性が高く、追加番号を設定することで複数番号を管理できます。ただし、利用できるチャネル数は限られているため、着信が集中する業種ではやや力不足になることがあります。現在ではサービスの終了も進んでおり、今後の長期運用には注意が必要です。
光回線・クラウドPBXなら柔軟なチャネル増設も可能
光回線やクラウドPBXを利用したIP電話サービスでは、同時通話数を柔軟に増減できるのが大きな強みです。数チャネルから数十チャネル、場合によっては100チャネル以上まで対応できるため、コールセンターや大規模オフィスでも安心して運用できます。また、番号の追加や変更も短期間で行えることが多く、コスト面でも効率的です。規模の拡大やテレワーク導入を見据えた企業にとって、将来性の高い選択肢といえるでしょう。
電話番号を増やす方法とその費用感
法人電話で複数の番号を利用する場合、「どうやって番号を増やすのか」「いくらかかるのか」という点は必ず押さえておきたいポイントです。追加番号を取得する方法はいくつかあり、回線契約の種類や利用するサービスによって費用や柔軟性に大きな差があります。
番号を追加する際の初期費用・月額費用の目安
番号を追加するには、まず回線事業者に申し込みを行います。
- 初期費用:1番号あたり数千円〜1万円程度が一般的です。
- 月額費用:1番号ごとに数百円〜1,000円程度で利用できる場合が多いです。
ただし、アナログ回線やISDN回線の場合は追加できる番号数に限界があります。一方、クラウドPBXを利用すると、追加費用を抑えつつ柔軟に番号を増やすことが可能です。
回線を増やす vs 番号だけ増やす、どちらがコスパ良い?
- 回線を増やす場合:同時通話数も増えるため、大量の着信や発信が必要な企業に適しています。ただし、初期費用や月額料金が高くなりやすい点がデメリットです。
- 番号だけ増やす場合:コストを抑えつつ、FAX専用番号や部署ごとの直通番号を設定できます。ただし、同時通話数は変わらないため、通話が集中すると「話し中」になりやすい点に注意が必要です。
コストと業務効率のバランスを考え、どちらを優先すべきかを判断すると良いでしょう。
導入前に注意すべき落とし穴とは?
番号を増やす際には、いくつかの注意点があります。
- 回線の種類による制限:アナログ回線やISDNは増設できる番号やチャネル数に限界があります。
- 運用コストの見落とし:番号を増やせばそれだけ月額費用も発生するため、長期的なコストを試算することが大切です。
- 社内の運用体制:番号を増やしても、誰がどの番号に対応するのかが決まっていなければ、逆に混乱を招く可能性があります。
これらの点を踏まえたうえで、コストと運用の最適解を探すことが重要です。
導入前にチェック!複数番号を使うときの注意点
複数番号を導入することで業務効率が上がる一方、仕組みを正しく理解していないと「せっかく導入したのに思ったように使えない」という事態になりかねません。
ここでは導入前に押さえておくべき注意点を整理します。
電話回線の種類による制限に注意
アナログ回線・ISDN回線・光回線(IP電話)など、利用する回線の種類によって「追加できる番号数」や「同時通話数」に大きな違いがあります。特にアナログ回線は1回線1通話が基本のため、複数番号を設定しても同時利用には制限があります。導入前に、自社の回線がどの方式かを必ず確認しましょう。
通話チャネル数が足りないと“話し中”に…
番号を増やしたとしても、チャネル数が不足していれば同時着信時に「話し中」となり、顧客を逃してしまう恐れがあります。特にコールセンターや問い合わせ窓口では、チャネル数を見誤ると大きな機会損失につながります。想定される同時着信数を見積もり、余裕を持ったチャネル設定を行うことが重要です。
社内運用ルールを決めてトラブル防止
番号を部署や担当者ごとに割り当てた場合、「どの番号に誰が対応するのか」を明確にしなければ社内で混乱が生じることがあります。
たとえば、営業直通番号にかかってきた電話を誰が取るのか、留守番時の転送先をどうするのか、といったルールを事前に整備しておくことが大切です。運用ルールを定めておけば、番号を増やした効果を最大限に活かせます。
法人電話の最適な番号構成は?利用目的別のおすすめパターン
複数番号の導入は、企業の規模や業務内容によって最適な構成が異なります。単純に「番号を増やす」だけではなく、用途に合わせた組み合わせを考えることで、業務効率や顧客満足度を大きく高められます。
ここでは代表的なパターンを紹介します。
小規模オフィスなら「代表番号+直通番号」
社員数が少ない小規模オフィスでは、1つの代表番号に加えて、必要に応じて直通番号を追加する方法が有効です。例えば、代表番号は総合受付用にし、営業担当者に直通番号を割り当てれば、顧客はスムーズに担当者とつながります。番号を増やしすぎず、シンプルに運用できるのがメリットです。
部署ごとの管理強化には「番号追加+内線管理」
部署ごとに業務が分かれている中規模企業では、各部署に直通番号を用意し、さらに社内では内線管理を組み合わせるのがおすすめです。これにより、顧客は最初から目的の部署につながり、社内では内線で効率よくやり取りができます。外部対応と内部管理をバランスよく最適化できる構成です。
全国展開企業なら「拠点別番号+IP電話活用」
複数拠点を持つ企業では、拠点ごとに番号を用意しつつ、IP電話を導入すると便利です。インターネット環境があれば場所を問わず発着信でき、出張やテレワークでも代表番号での対応が可能になります。拠点を横断した一体的な運用にも役立ちます。
IP電話なら番号も通話数も自由自在|おすすめはSUBLINE(サブライン)
従来の固定電話回線は、番号を増やすにも回線工事や追加機器が必要で、費用も手間もかかりました。しかし、インターネットを利用するIP電話サービスなら、番号や利用環境をもっと柔軟に拡張できます。
特にSUBLINE(サブライン)は、スマホで法人用の番号をすぐに利用できる手軽さと、コストパフォーマンスの高さが好評でおすすめです。
SUBLINE(サブライン)とは?050番号がすぐに使える法人向けサービス

SUBLINE(サブライン)は、お手持ちのスマホにアプリをインストールするだけで、プライベート番号の他にもう一つ、仕事用の050電話番号が持てるサービスです。
個人スマホにアプリを入れるだけなので、端末を新たに支給する必要がありません。
出張やテレワークがある人、社用携帯を持つのがメンドウな人、社用携帯のコストを削減したい人に最適です。
また、1名から100名以上まで、企業規模問わず導入しやすいのも特徴です。
詳しくは公式サイトをご覧ください。
公式サイト https://www.subline.jp/
よくある質問
複数番号を導入するにあたり、多くの企業が抱える疑問をまとめました。導入前にチェックしておくことで、安心して最適な法人電話環境を整えられます。
電話番号を2つ持つ方法はありますか?
はい、可能です。1つの回線契約で追加番号を取得する「ダイヤルイン」サービスを利用すれば、代表番号とは別にFAX専用番号や直通番号を設定できます。また、クラウドPBXを導入すれば物理回線に依存せず、複数番号を柔軟に追加できます。
NTTの1回線で2番号は取れますか?
NTTの固定電話回線でも「ダイヤルイン」を利用すれば1回線で複数の番号を持つことが可能です。ただし、回線の種類(アナログ、ISDN、光回線)によって追加できる数や同時通話数に制限があるため、事前確認が必要です。
電話番号の追加にはどれくらいの費用がかかりますか?
回線事業者を通じて番号を追加する場合、初期費用は数千円〜1万円程度、月額費用は1番号あたり数百円〜1,000円程度が相場です。クラウドPBXの場合は、追加番号の月額費用が低価格に抑えられるケースが多く、コストを気にする企業に向いています。
電話回線を複数利用するメリットは?
複数回線を契約すると、同時通話可能数が増えるため、着信が集中しても「話し中」になりにくいのがメリットです。特に問い合わせや受注が多い企業では、複数回線での運用が機会損失を防ぎます。
クラウドPBXは本当に固定電話の代わりになる?
はい。クラウドPBXはインターネット経由で会社番号の発着信ができる仕組みで、固定電話機がなくてもスマホやPCで運用可能です。高音質で安定した通話環境を実現しており、テレワークや外出先でも安心して使えます。
SUBLINEで複数番号を管理する方法は?
SUBLINEでは、オンライン管理画面から簡単に番号の追加や設定変更が可能です。営業用、サポート用など用途に応じて複数番号を管理でき、さらに外出先でも会社番号で発着信できます。導入コストが低く柔軟性が高いため、法人電話の複数番号運用に非常に適したサービスといえます。
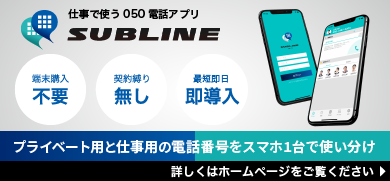

無料でお試しいただけます!
WEBで完結!最短即日で導入完了!
PROFILE

-
株式会社インターパーク/SUBLINEプロジェクトリーダー・マーケティング担当
中途で株式会社インターパークに入社。
仕事で使う050電話アプリSUBLINE-サブライン-のカスタマーサポート担当としてアサイン。
カスタマーサポートを経て、現在は事業計画の立案からマーケティング担当として事業の推進・実行までを担当。
過去、学生時代には2年間の海外留学を経験。