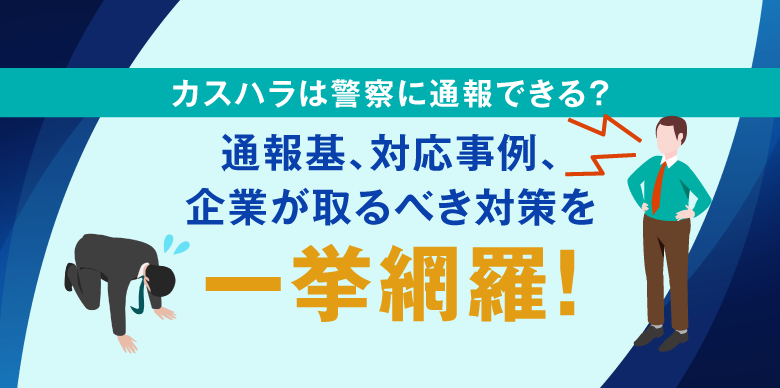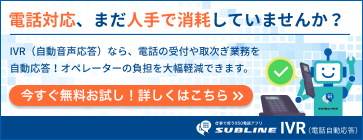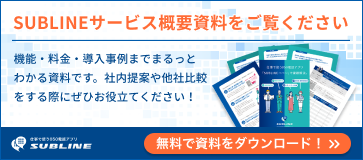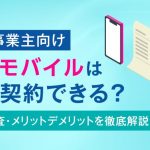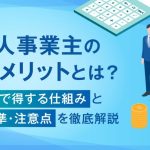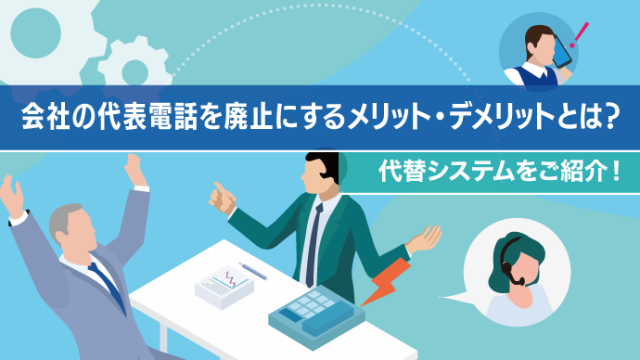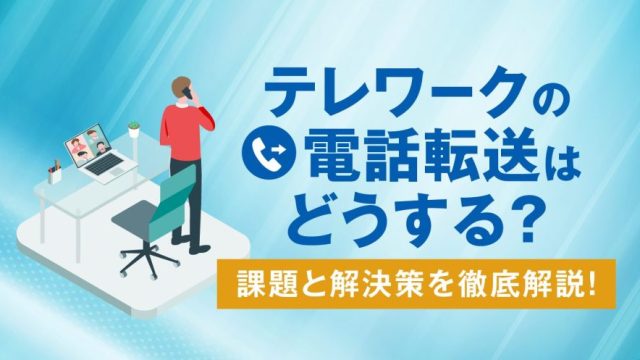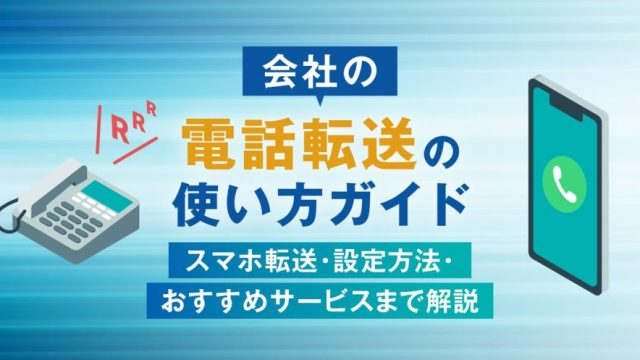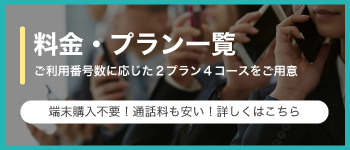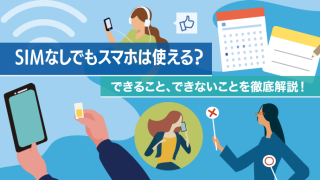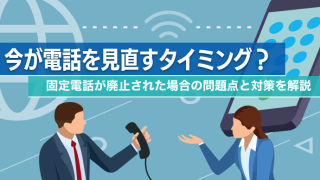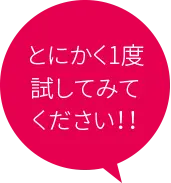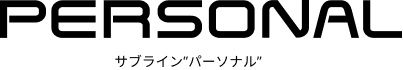カスタマーハラスメントは警察に通報できる?
本記事では、通報できるケース、手順、事例、企業ができる対策まで詳しく解説します。また、おすすめのIVR(自動音声応答)ツールもご紹介します。
カスハラとは?定義と具体例をわかりやすく解説
カスタマーハラスメント(略してカスハラ)は、企業や店舗の従業員に対して、顧客や取引先などが社会的常識の範囲を超えて不当な要求や言動を繰り返す行為を指します。正当なクレームとは異なり、精神的・肉体的な負担を与える悪質なケースが多く、近年、企業の労務管理上の重大な課題として注目されています。
カスタマーハラスメントの基本的な定義
カスハラの定義は法令で明確に定められているわけではありませんが、厚生労働省は以下のように整理しています。
「顧客や取引先からの著しい暴言・暴力・脅迫、不合理な要求、継続的なクレームなどにより、労働者の就業環境を害する行為」
これは、従業員が就労する上で安全かつ健康な職場環境を維持するための概念として定義されています。つまり、顧客であっても「何を言っても許される」わけではなく、常識を逸脱した行為はハラスメントと認定されうるということです。
実際に現場で起きているカスハラの具体例
現場でよく報告されるカスハラには以下のような事例があります。
- 電話対応での繰り返される罵倒・怒鳴り声・人格否定
- 店頭での土下座要求、長時間の居座り
- クレーム対応時に私生活や容姿への執拗な中傷
- 些細なトラブルを理由にした訴訟やSNSでの拡散脅迫
- スタッフの自宅やSNSを突き止めたストーキング的行為
これらはいずれも、従業員の心身に重大なストレスを与え、離職やメンタル不調の原因にもなっています。特に飲食業・小売業・コールセンター・介護施設など接客頻度の高い業種で多発しています。
増加するカスハラ被害と社会的背景
カスハラが急増している背景には、顧客側の「過剰なサービス要求意識(カスタマイズ志向)」や、「クレーム=正義」という誤解、SNS時代の“炎上リスク”を盾にした威圧行為の横行があります。
また、企業が「お客様第一主義」を過剰に掲げるあまり、従業員を守るルールが曖昧なまま放置されているケースも少なくありません。社会全体でのハラスメント認識が高まるなかで、企業には「顧客と従業員の両方を守る」視点が求められています。
カスハラは警察に通報できる?
カスハラの中には、明らかに刑法に触れるような悪質な行為も含まれており、状況によっては警察に通報や相談することが可能です。しかし、すべてのカスハラが警察の介入対象となるわけではないため、どのような場合に通報できるのか、判断基準を明確にしておくことが重要です。
警察が介入できるカスハラの代表例
警察が動く可能性が高いカスハラの行為は、以下のように「刑法上の犯罪」に該当するものです。
- 暴行罪・傷害罪:手を出された、物を投げつけられたなど
- 脅迫罪:「お前の会社を潰す」「家に行くぞ」など、生命・自由・名誉・財産に対する害悪の告知と受け取れる発言
- 強要罪:土下座を強制された、業務に支障をきたすよう強制された
- 威力業務妨害罪:長時間のクレーム電話や店舗への居座り
- 名誉毀損・侮辱罪:公共の場やSNSで誹謗中傷をされた
これらに該当する場合、被害届の提出や110番通報の対象となる可能性があります。特に人命や安全に関わる内容であれば、即時通報が推奨されます。
通報できるかの判断基準(脅迫・暴行・強要罪など)
通報が妥当かどうかを判断するには、以下の観点から冷静に整理することが必要です。
- 言動の内容が明確な違法行為にあたるか
感情的な怒声と「脅迫」は別物です。「○○しないと殺す」などの条件付きの威迫は脅迫罪の可能性があります。 - 業務妨害が継続しているか
店舗に居座って他の顧客の来店を妨げたり、長時間電話をかけ続けて業務を妨害している場合、警察が介入しやすくなります。 - 録音・録画など証拠が残っているか
証拠が明確であるほど、警察も事実確認をしやすくなります。
判断に迷う場合は、警察の生活安全課への事前相談や、社内の法務担当・弁護士と連携して対応方針を確認するのが望ましいです。
店舗で警察を呼ぶべきか迷ったときの判断ポイント
現場で「警察を呼ぶべきかどうか」迷うことは少なくありません。次のような状況では、通報を前提に行動を検討してください。
- 顧客が暴力的・威圧的な態度を継続している
- 従業員が恐怖心を感じて業務継続が困難な状態
- 第三者(他の客やスタッフ)に危害が及ぶ可能性がある
- 過去にも同一人物によるハラスメント歴がある
また、状況を動画や音声で記録しつつ、通報することは、後の証拠保全にもつながります。企業としても「スタッフの安全を最優先する」方針を明確にし、マニュアルに通報基準を盛り込んでおくことが推奨されます。
カスハラで警察に通報・相談する際の手順
カスハラ被害を受けた際に、いざ警察に通報しようとしても、「何を準備すればいいのか」「どこに相談すべきなのか」と戸惑うことも少なくありません。
ここでは、現場で混乱せずに対応できるよう、警察への通報・相談の基本的な流れと準備すべきポイントを具体的に解説します。
通報する前に確認すべき証拠(録音・映像・メモ)
警察が事実確認を行う際には、証拠の有無が極めて重要です。以下のような証拠を可能な範囲で残しておきましょう。
- 通話録音:コールセンターや電話対応時に録音した音声。日時と発言内容が明確であれば有力。
- 防犯カメラ映像:店舗や施設内でのカスハラ行為が映っている映像。録画保存の期間に注意。
- 現場のメモや記録:発生日時、言動の内容、対応者、経過などを記録したメモや報告書。
- 第三者の証言:同僚や他の顧客などの証言も有効な補助材料になります。
証拠が複数あるほど、警察も動きやすくなります。特に法人の場合は、あらかじめ証拠保全マニュアルを整備しておくと有利です。
110番通報と生活安全課相談の違い
カスハラに対する警察への連絡には、大きく2種類の窓口があります。それぞれの違いを理解して使い分けましょう。
【110番通報】
- 緊急性が高く、現場対応が必要なとき(暴力・威嚇・危険がある)
- 通報後、警察官が現場に駆けつける
- 原則として「今すぐ対応してほしい」ケース
【生活安全課への相談】
- 緊急ではないが、継続的な被害や脅迫などを相談したい場合
- 証拠を持って署や交番に出向く必要がある
- 書面で被害届や相談記録を残すことが可能
迷った場合は110番して状況を説明すれば、適切な対応窓口へ案内されることがほとんどです。
被害届を出すまでの流れと必要書類
カスハラの内容が刑事事件に該当する場合、被害届を出すことが可能です。その流れは以下の通りです。
- 証拠の準備
録音・メモ・映像などを整理して持参。 - 警察署の生活安全課や最寄り交番に相談
その場で被害届の受理可否が判断される。 - 被害届の作成と提出
所定の書式に沿って記入。警察官のヒアリングを受けながら進行。 - 警察による捜査開始(場合によっては事情聴取や立件)
なお、匿名での相談も可能ですが、捜査を進めるには基本的に「被害者本人の申し出」が必要になります。
弁護士・社労士と連携するタイミング
企業としてカスハラ対応を行う際、警察対応と並行して弁護士や社労士との連携も視野に入れておくべきです。
- 顧客対応マニュアルの整備
- 法的リスクの判断と助言
- 損害賠償請求や仮処分申請の代理
- 従業員への説明責任と安心感の確保
特に、顧客からの報復的なクレームや訴訟リスクを警戒する場合、事前に専門家と相談しながら対応方針を固めておくことで、企業としての信頼性も高まります。
実際に警察が対応したカスハラの事例
カスハラ行為が刑事事件として警察に扱われたケースは、近年着実に増加しています。
ここでは、実際に立件や書類送検に至った事例を通して、どのような行為が法的に問題視され、どこまでが“警察が動くライン”であるのかを具体的に解説します。
強要・暴行・脅迫で書類送検されたカスハラ例
以下は、実際にニュース報道などで明らかになった、書類送検に至った事例です。
- 某飲食店での土下座強要事件
来店時の料理内容に不満を持った高齢男性が、店員に対して「土下座しないと訴える」と執拗に詰め寄り、録音された音声を証拠に強要未遂罪で書類送検。 - コールセンターでの連続脅迫電話
通信会社のカスタマーサポートに対し、1日に何度もクレーム電話を繰り返し、「殺すぞ」などの暴言を録音され、脅迫罪・威力業務妨害罪で立件。 - 百貨店内での暴行事件
対応した女性店員に商品説明が不十分だと激高し、髪を掴むなどの暴行に及んだ顧客が、現行犯逮捕→暴行罪で起訴。
これらの事例に共通するのは「証拠が残っていたこと」と「継続的または重大な影響を与えていたこと」です。事後対応の際にも、証拠の重要性がよく分かります。
迷惑防止条例が適用された事例
刑法とは別に、各自治体が制定する迷惑防止条例でもカスハラ行為が取り締まられる場合があります。
- コンビニ店内での長時間の罵声
レジ対応への不満を理由に30分以上にわたり店員を怒鳴り続けた客に対し、周囲の通報により東京都迷惑防止条例違反で摘発。 - 病院での看護師への威圧行為
診察内容に納得がいかないと怒鳴り、ドアを蹴るなどの威嚇行為が確認され、迷惑行為防止条例違反で書類送検。
条例の運用は地域差があるものの、公共の場での悪質な言動はこれらの法律によって対応可能です。事業者は地元の条例も確認しておくと安心です。
刑事事件になったか否かを分けた要因とは
実際に警察が動いたかどうかを分けたポイントは主に以下の3点です。
- 明確な証拠の有無
録音・録画・目撃者の証言など、客観的に確認できる材料があるか。 - 継続性・悪質性の程度
一時的な口論ではなく、長期間にわたる執拗な行為か、または身体的危害の恐れがあるか。 - 業務への実害の有無
クレームが業務を著しく妨害したか、他の顧客に影響が出たか。
上記が揃っている場合、警察も動きやすくなります。逆に、感情的なトラブルだけでは「民事不介入」とされる可能性が高いため、冷静な記録と報告体制が企業に求められます。
弁護士相談や損害賠償請求によるアプローチ
悪質なカスハラに対して、警察が動かなくても法的手段を通じて対処することは可能です。たとえば、以下のような民事訴訟や通知が考えられます。
- 内容証明郵便の送付:これ以上の接触や威嚇を止めるよう法的に警告
- 損害賠償請求訴訟:精神的苦痛や業務妨害による実害に対する賠償を請求
- 仮処分申立て:店舗や施設への接近禁止を求める
弁護士が介入することで、相手側が態度を改めるケースも多くあります。早期に専門家と連携することで、対応が後手に回るのを防げます。
企業としてできるカスハラ対策と警察との連携
カスハラは個人の対応に任せてしまうと、従業員の心身に深刻なダメージを与えるだけでなく、企業の評判や安全管理体制にも悪影響を及ぼします。組織としてカスハラに毅然と立ち向かうためには、「社内整備」と「警察・外部機関との連携」の両輪での対策が不可欠です。
就業規則・マニュアルへの明記と社内教育
まず重要なのは、企業として「カスハラを許容しない」というスタンスを明文化することです。
- 就業規則や服務規程に「カスハラ対応の基準と行動方針」を明記
- カスハラに該当する具体的言動の例を社内に周知
- 対応手順や通報ルートを記載したマニュアルを整備
- 新入社員・中堅社員・管理職向けの階層別研修を実施
これにより、現場の従業員が「どう対応すればいいのか」「報告していいのか」を明確に理解でき、初期対応がブレなくなります。また、企業の安全配慮義務(労働契約法第5条)に基づいた対応として、法的リスクの低減にもつながります。
警察との事前連携・相談ルートの確保
警察は「通報されたら動く機関」であると同時に、「予防的な相談にも応じてくれるパートナー」です。特にカスハラ対策においては、事前の関係構築が極めて重要です。
- 最寄りの警察署・交番に「生活安全課」などの担当者を確認
- 事件化していない段階でも相談可能
- 対応記録や証拠保全方法についての助言を受ける
- 地域の防犯協会や商店会と合同でカスハラ研修を実施
企業が警察と事前に連携していることが社内外に伝われば、顧客に対しても抑止力となります。特に複数のカスハラ事案が発生している場合は、組織として警察との連携体制を整備しておくべきです。
コールセンターや店舗での対策事例紹介
実際に対策に成功している企業の事例には、以下のような工夫があります。
- 大手小売チェーン:暴言や威圧行為があった際に再来店を拒否できる「禁止顧客リスト制度」を導入。出入り禁止措置は警察と相談の上で実施。
- 通信系コールセンター:一定回数以上のクレーム発信者には、自動音声で「通話が録音されている」旨を通知。対応スタッフへの精神的負担を軽減。
- 医療機関:診察室内に録音・録画システムを設置し、患者からのハラスメント抑止に活用。
このような事例は、従業員の安全と尊厳を守ると同時に、企業としての対外的信用向上にも寄与します。自社に合った対策を柔軟に取り入れる姿勢が求められます。
外部相談窓口・IT活用によるカスハラ対策
カスハラ対応は社内だけで抱え込むべきものではありません。近年では、弁護士や社労士など外部の専門家によるサポートや、ITツールを活用した効率的かつ従業員負担の少ない対策が広がっています。
ここでは、外部連携とシステム導入の観点から有効な取り組みを紹介します。
弁護士・社労士・外部相談窓口の導入例
カスハラ対応において、社内の管理者や現場責任者がすべてを背負うことは現実的ではありません。
次のような第三者機関の支援を活用することで、リスク回避と負担軽減を両立することが可能です。
- 顧問弁護士の設置
カスハラが発生した際の対応判断、警察への通報基準、損害賠償請求の検討などに即時対応可能。 - 外部通報窓口(社外相談ホットライン)の設置
従業員が安心してカスハラ被害を報告できる体制を構築。匿名対応も可能なサービスも多数。 - 社会保険労務士の活用
就業規則の整備や安全配慮義務の観点から、法的に適切な運用を支援。
また、自治体や業界団体が運営する無料相談窓口を併用することで、コストを抑えながら多面的な対策が可能です。
IVR(自動音声対応)の活用でカスハラを未然に防ぐ
カスハラが特に多いのが、電話によるクレーム対応です。対面と違って匿名性が高く、怒りの感情がエスカレートしやすいため、スタッフへの心理的ダメージも深刻です。
この問題に対して、IVR(自動音声応答)システムの活用が効果的な対策として注目されています。
IVR(自動音声応答)ならSUBLINE(サブライン)がおすすめ
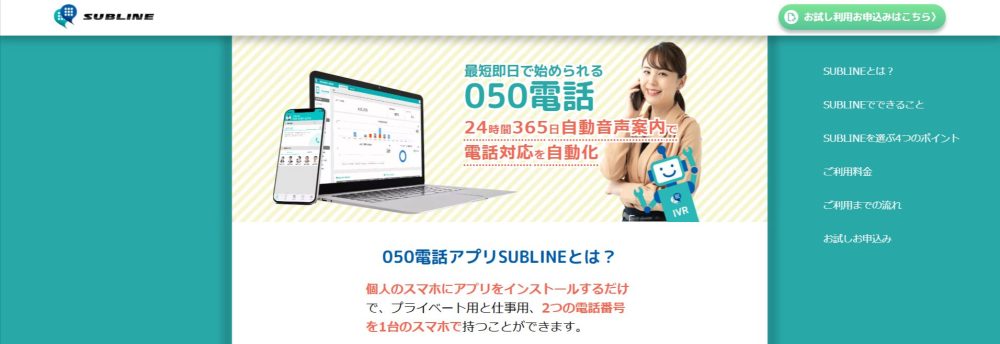
SUBLINE(サブライン)は、IVR(自動音声応答)を搭載しているのでかかってきた電話に対し自動音声ガイダンスで受付、対応することが可能です。たとえば「この通話は応対品質向上のため録音させていただいております」といったメッセージを事前に設定しておくだけで、クレーマーのブロックにつなげることができます。
SUBLINE(サブライン)を導入することで、1次対応の段階でハラスメントの芽を摘むことができ、従業員の精神的負担と離職リスクを大幅に減らすことができます。特に中小企業やコールセンター業務のある企業では、早期導入の価値が高いソリューションです。
導入までの流れや詳しいプラン内容は「SUBLINE 公式サイト」をご覧ください。
SUBLINE 公式サイトを見る
よくある質問(FAQ)
カスハラと警察対応に関して、現場からよく寄せられる疑問や不安に対して、専門的視点からわかりやすくお答えします。
カスハラをどこに通報すればよいですか?
カスハラが刑事事件に該当する可能性がある場合は、迷わず警察署や交番、あるいは緊急時には110番に通報してください。
暴力・脅迫・強要などの行為があれば、警察の生活安全課に相談するのが基本です。
一方、違法性が明確でないケースでも、法テラスや弁護士・社労士などの第三者機関への相談が有効です。企業内に通報制度(内部通報・外部窓口)があれば、そこを経由する形も選択肢となります。
クレーマーに対して警察を呼んでもいいですか?
呼んでも問題ありません。特に以下のようなケースでは、正当な判断として警察を呼ぶべきです。
- 暴言や脅迫がエスカレートしている
- 身体的危険や業務妨害が発生している
- スタッフが精神的ショックを受けている
「お客様だから我慢しなければならない」という時代ではありません。スタッフの安全と業務の正常性を守るためにも、躊躇なく通報しましょう。
カスハラはどのような罪になりますか?
状況によっては、以下のような刑法違反に該当します。
- 脅迫罪(刑法222条)
- 暴行罪・傷害罪(刑法204・208条)
- 強要罪(刑法223条)
- 威力業務妨害罪(刑法234条)
- 名誉毀損・侮辱罪(刑法230・231条)
これらは刑事罰の対象であり、警察が捜査や逮捕を行う正当な根拠となります。
カスハラでも警察が動かないことはありますか?
あります。以下のようなケースでは、警察が「民事不介入」として介入を控える可能性があります。
- 違法性が明確でない単なる口論
- 暴力や脅迫が証明できない
- 客観的証拠が存在しない(録音や映像がない)
このような場合でも、記録を残しておけば、継続的な被害の証拠として活用できるため、将来的な再通報や法的対応につなげることができます。
カスハラ対応をマニュアル化するにはどうすれば?
まずは以下の3点を軸に、マニュアルを整備しましょう。
- カスハラに該当する行為の定義・例示
- 発生時の対応手順(初動〜記録〜報告)
- 通報基準・警察や専門機関との連携ルール
マニュアルは一度作って終わりではなく、実際の事例を踏まえて定期的に見直しを行うことが重要です。弁護士や社労士の監修を受けることで、法的な裏付けを持った運用が可能になります。
カスハラ通報で逆に訴えられることはありますか?
可能性はありますが、適切な対応をしていれば過度に恐れる必要はありません。
たとえば、誤認で通報したとしても、それが「合理的な判断」や「緊急避難」に基づくものであれば、違法性は否定される場合がほとんどです。
ただし、通報の際に不必要な人格攻撃や名誉毀損にあたる言動をしてしまった場合は、逆に訴えられるリスクもあります。通報・記録・報告はいずれも「冷静かつ事実に基づく」ことが大原則です。
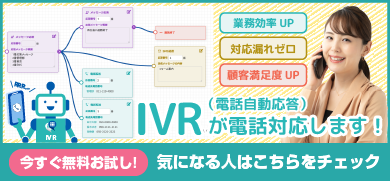
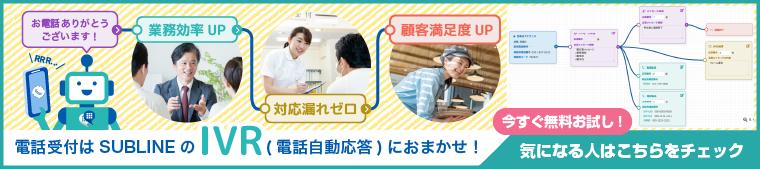
不要な電話対応にサヨナラ!
WEBで完結!無料お試しが可能です!
PROFILE

-
株式会社インターパーク/SUBLINEプロジェクトリーダー・マーケティング担当
中途で株式会社インターパークに入社。
仕事で使う050電話アプリSUBLINE-サブライン-のカスタマーサポート担当としてアサイン。
カスタマーサポートを経て、現在は事業計画の立案からマーケティング担当として事業の推進・実行までを担当。
過去、学生時代には2年間の海外留学を経験。