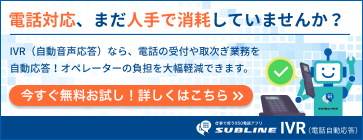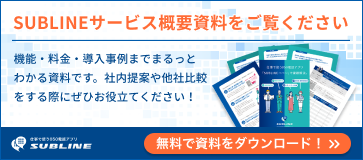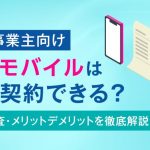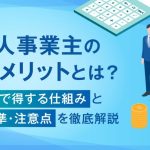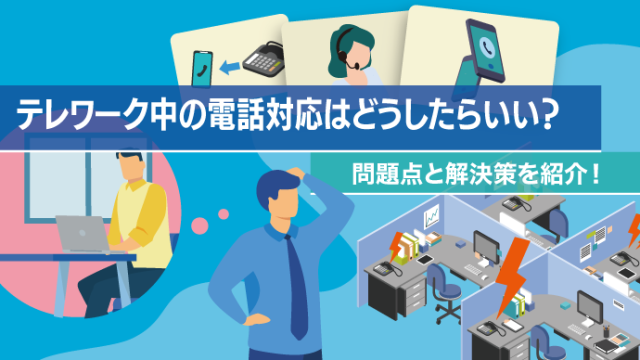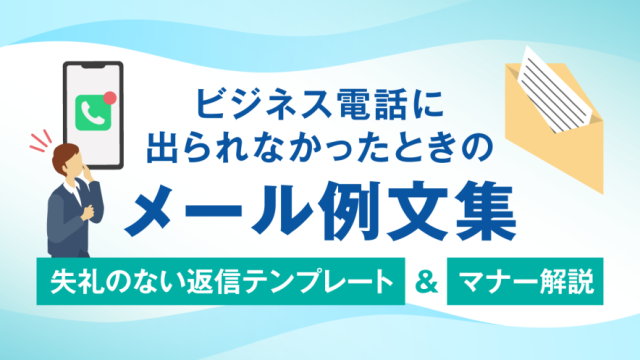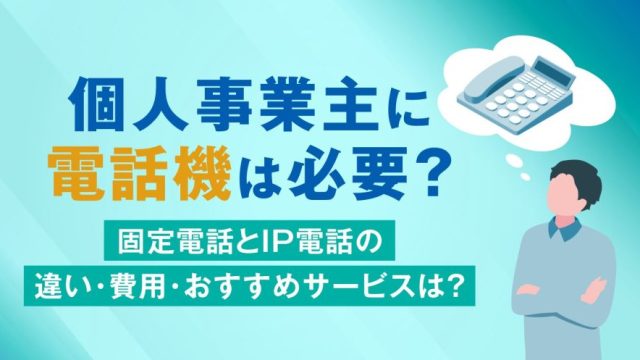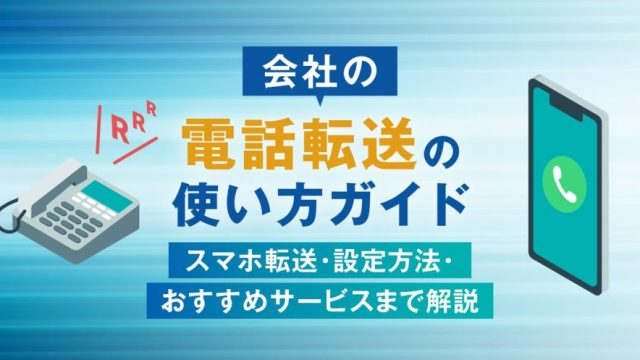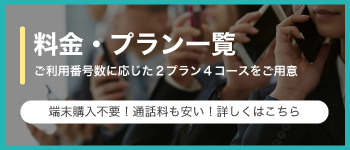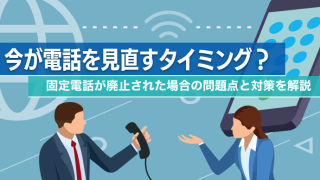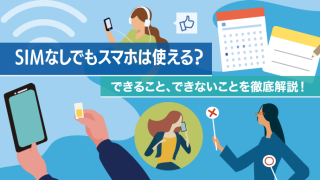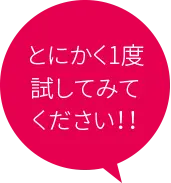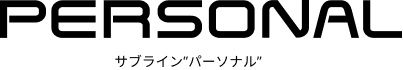本記事では、効果的な対応方法から、法的対処、社内ルール事例、再発防止策まで触れつつ、おすすめのIVR(自動音声応答)ツールとその予防策もご紹介します。
しつこいクレーム電話とは?まずは現状を正しく把握する
顧客対応の中でも特に難しいのが、繰り返し電話をかけてくる「しつこいクレーム」への対応です。適切に対応しなければ、業務の妨げになるだけでなく、従業員の心身にも大きな影響を与えます。
まずは、一般的なクレームと悪質なケースの違いを整理し、なぜ何度も電話してくるのか、その背景を理解しましょう。
一般的なクレームと悪質クレーマーの違いとは
一般的なクレームとは、商品やサービスに対する具体的な不満を伝えるもので、企業側が誠実に対応することで解決に向かうことが多いです。一方、悪質なクレーマーは「金銭要求」「謝罪の強要」「何度も同じ内容を繰り返す」「業務妨害目的」など、本来のクレームの域を超えて、精神的・時間的に追い詰める行為が特徴です。
特に電話による執拗な要求は、会話の記録が残りにくく、担当者個人に圧力がかかりやすいため、早期に線引きと対策が必要です。
なぜ電話で何度もクレームしてくるのか?心理的背景を知る
しつこいクレームには、単なる不満の表出だけでなく、次のような心理が絡んでいるケースが多くあります。
- 自己重要感の誇示:「自分は特別扱いされるべき」という承認欲求
- 相手の反応を見たい:謝罪や言い訳を何度も引き出そうとする
- 過去の対応への不満の執着:解決済でも納得できておらず、再び蒸し返す
- ストレスのはけ口として利用:本来の原因が別にあることも
こうした心理を理解することは、「共感しつつも距離を取る」対応の助けになります。
担当者を変えても電話が止まらない理由
多くの企業が、「担当を変えれば落ち着くのでは」と人を交代させますが、根本的な対応方針が一致していない限り効果は薄いと言えるでしょう。
クレーマーは、対応者の発言の違いや過去の言動の矛盾を突いてくるため、担当者ごとに温度差や対応内容が異なると、「再度の要求」を引き起こす原因になります。
そのため、記録の共有・社内統一の対応指針・組織的な対応体制が重要です。「誰が出ても同じ対応である」と示すことが、クレームの長期化を防ぐ鍵になります。
クレーム電話への正しい対応ルールを確認しよう
しつこいクレーム電話に対しては、場当たり的な対応ではなく、一定のルールに基づいた冷静な対応が不可欠です。
ここでは、初期対応の基本から、通話の切り方、記録の取り方まで、実務で活用できるポイントを具体的に紹介します。
初期対応で重要な「冷静」「共感」「境界線」の3原則
初期対応で最も大切なのは、感情的にならず、相手の話を一度受け止めることです。クレームの多くは、話を最後まで聞くだけでも沈静化することがあります。
- 冷静:どれほど怒鳴られても、声色・語調を乱さず対応する
- 共感:「ご不便をおかけして申し訳ございません」など、不満の背景に共感を示す
- 境界線:事実と感情を分け、要求が不当な場合は毅然とした態度をとる
クレーマーは、「弱い対応者」を見つけると攻撃を強める傾向があります。誠意と毅然さのバランスが求められます。
長時間通話を防ぐための効果的な言い回し例
長時間の電話を避けるには、通話の主導権を握り、要点を整理させる言い回しが有効です。以下は実践的なフレーズ例です。
- 「○○様のお話を正確に把握するため、要点を整理させていただいてもよろしいでしょうか?」
- 「お話しいただいた内容をもとに、社内で確認したうえで、折り返しご連絡差し上げてもよろしいですか?」
- 「このまま長くなりますと、他のお客様への対応に支障が出てしまいますので、一度お電話を切らせていただきます」
「聞き続ける姿勢」を維持しながらも、時間制限を明示し、合理的に通話を終了させる言い回しがポイントです。
応対履歴を残す:録音とメモの取り方と注意点
しつこいクレーム対応では、記録が最大の防御になります。電話応対の録音と要点メモを必ず残しましょう。
- 録音:通話録音は原則合法(自分が会話の当事者であれば)。録音前に「通話は記録しております」と伝えると抑止効果も。
- メモ:日時、発言内容、感情の変化、要求内容を正確に記録
- 共有:記録は担当者個人ではなく、社内共有フォルダやCRMに残す
記録があれば、万が一法的対応に発展した場合でも、証拠として活用できます。
クレーム電話を切るタイミングとその正当性
「電話を勝手に切るのはNG」という誤解がありますが、業務に支障をきたす、あるいは暴言が続く場合は終了してよい正当性があります。
切る前に以下のように警告を伝えましょう。
- 「大変申し訳ありませんが、これ以上の会話が続きますと業務に支障が出てしまいますため、今回のご対応はこれで終了させていただきます」
- 「録音のうえで、これ以上の暴言があれば、対応を打ち切らせていただきます」
その後、同じ番号からの着信に対し、社内ルールに基づいた対応(出ない・記録だけするなど)に切り替えることが望ましいです。
社内でできるクレーム電話への対策ルールの整備方法
しつこいクレーム電話に対処するには、個人の経験やスキルに頼るのではなく、全社的な対応ルールの整備が不可欠です。属人的な対応を排除し、再現性のある仕組みを作ることで、業務の安定と社員の安心感が両立できます。
応対ルールに盛り込むべき5つの項目
ルールを作成する際に、最低限盛り込むべき基本項目は以下の5点です。
- クレームの定義と対応範囲の明確化
→ どのようなケースが「正当なクレーム」で、どこからが「悪質」なのかを明示 - 初期対応の流れ(あいさつ・傾聴・共感・確認)
→ 対話の型をパターン化し、属人的・感情的な応酬を回避する - 記録の取り方と記録内容の統一フォーマット
→ 後続対応の質とスピードを担保するため - エスカレーションの基準と手順
→ 担当者が抱え込みすぎず、上司や法務部に引き継げるルール - 対応終了・着信拒否の判断基準と文言例
→ 打ち切る判断を迷わせないための明文化
これにより、どの社員が電話に出ても一貫した対応が可能になります。
エスカレーション体制を明確にするメリット
クレーム対応におけるエスカレーション(上位者対応)のルールを明確にすることは、現場の心理的負担を軽減するうえで非常に効果的です。
- 対応中に「この件は上席が承ります」と伝えることで、相手のトーンが和らぐ
- 一人で抱え込まず、精神的なセーフティネットができる
- 記録に基づいて判断すれば、対応の正当性が客観的に担保される
また、マネージャーや法務担当者には、エスカレーション対応専用のトーク例や判断フローを別途整備することが望ましいです。
社内共有すべき情報と記録ルールの作り方
属人的な対応を防ぐには、記録の標準化と共有が鍵です。以下のルールを定めておきましょう。
- 応対記録には「発言内容」「対応者名」「感情の変化」「要求事項」を明記
- CRMや社内共有フォルダなどに記録を一元化
- 繰り返し電話があった場合に対応履歴をすぐ確認できる体制
情報共有ができていれば、「誰が対応しても同じ対応ができる」体制となり、クレーマーが相手を選んで攻撃してくるリスクを減らせます。
定期的なクレーム対応研修とメンタルケアの重要性
但し、ルールを整備するだけでは現場力は育ちません。年に1〜2回のクレーム対応ロープレ研修を通じて、現場の対応力を高めることが重要です。
また、以下のメンタルケアも並行して実施すべきです。
- 対応者の心のケア(面談・カウンセリング)
- クレーム対応後の共有・振り返り(「自分だけが責められている」感をなくす)
- クレーム対応の評価制度(対応力を成果として評価する)
これにより、対応者が疲弊せずに継続的に業務に向き合える環境が整います。
法的にどうなの?しつこい電話が犯罪になるケースとは
しつこいクレーム電話がエスカレートすると、もはや「業務妨害」や「脅迫」といった刑法上の違法行為に該当する可能性があります。感情的なやりとりに終始せず、法的視点からの判断基準を知っておくことが、企業としてのリスク対策にもつながります。
名誉毀損・脅迫・強要・業務妨害に該当する事例
以下のような言動は、法的に「犯罪」に該当する可能性があります。
- 名誉毀損(刑法230条):「御社は詐欺企業だ」「SNSで悪評をばらまくぞ」など、事実か否かにかかわらず社会的評価を下げる発言
- 脅迫(刑法222条):「家に行くぞ」「覚悟しろ」などの言動があった場合
- 強要(刑法223条):「謝罪しろ!」「金を払え!」など、不当な義務を押し付ける要求
- 業務妨害(刑法234条):連続した電話で業務に支障が出ている場合
これらの言動が繰り返されるようであれば、記録を残した上で法的手段の検討が必要です。
警察や弁護士に相談すべき基準と判断のポイント
「どこまでがクレームで、どこからが犯罪か?」という線引きは非常に重要です。以下の基準を目安に判断するとよいでしょう。
- 暴言・脅しが含まれるか
- 1回だけでなく複数回、執拗に行われているか
- 担当者や会社全体への精神的・業務的被害があるか
- 謝罪・返金など、法的に不当な要求をされているか
上記に該当する場合、警察の生活安全課や、企業法務に強い弁護士への相談が推奨されます。証拠があれば、警察が注意指導や捜査に動くこともあります。
企業が法的措置をとる際に準備すべき証拠とは
法的措置をとる際、口頭だけの主張ではなく、客観的な証拠が求められます。準備すべきものは以下の通りです。
- 通話録音(日時・相手・内容を明記)
- クレーム対応記録(対応者・内容・経緯)
- メールやFAXなど書面によるやりとり
- 着信履歴・通話時間・回数のログ
これらは、警察相談や訴訟時に有力な証拠となり、企業の正当性を裏付ける材料になります。
着信拒否・通話遮断は法的に問題ないのか?
「しつこいクレーム電話を拒否してもよいのか?」という問いには、原則として問題ありませんと答えられます。
企業には、業務を適正に遂行する自由があるため、業務を著しく妨げる行為に対して通話を制限することは正当な権利とされています。ただし、以下の注意点があります。
- 一方的な遮断の前に、記録を残したうえで「対応を終了する旨」を伝える
- その後は、録音・記録だけを行い、必要に応じて法的措置へ
過度な応対継続は、従業員の心身にも悪影響を及ぼすため、防衛策としての着信拒否は許容されます。
クレーム電話を減らすために|IVR導入による予防策
クレーム電話の対応に追われる前に、「そもそも電話を必要以上に受けない」ための仕組みづくりが重要です。その一つが、IVR(自動音声応答)の導入です。
しつこいクレーム電話を未然に防ぎ、現場の負担を大幅に軽減することができます。
電話の一次対応を自動化するIVR(自動音声応答)とは?
IVR(Interactive Voice Response)は、電話の着信時に自動音声で案内を行い、用件やオペレーターごとに振り分けるシステムです。
たとえば、
- 「ご用件をお伺いします。商品についてのご質問は1番を…」
- 「この通話はサービス向上のため録音しております」
といった案内を流すことで、悪質クレーマーの威圧行為を抑止し、本当に必要な電話だけを人間が対応できる環境を構築できます。
SUBLINE(サブライン)のIVRでクレーム電話を未然に防ぐ
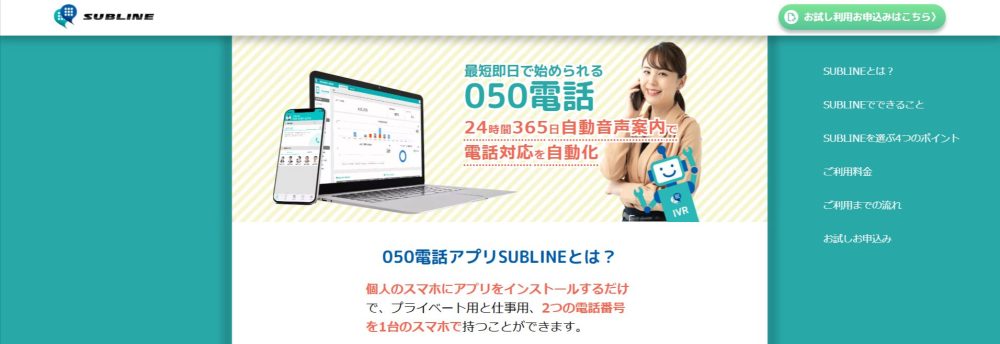
SUBLINE(サブライン)は、IVR(自動音声応答)を搭載しているのでかかってきた電話に対し自動音声ガイダンスで受付、対応することが可能です。たとえば「この通話は応対品質向上のため録音させていただいております」といったメッセージを事前に設定しておくだけで、クレーマートラブルのリスク軽減につなげることができます。
SUBLINE(サブライン)のIVRには、現場が必要とする機能が揃っています。
- 着信時の自動音声ガイダンス(クレームの一次遮断)
- 内容ごとの着信の振り分け(適切なオペレーター対応)
- 自動応答メッセージのカスタマイズ(企業ごとの対応方針に適応)
- 管理画面での着信ログの可視化
さらに、特別な設備投資なしで利用できる点も、導入ハードルが低い理由の一つです。
詳しくは公式サイトをご覧ください。
このように、電話対応の前に“フィルター”をかけることが、企業を守る第一歩となります。
よくある質問(FAQ)
しつこいクレーム電話対応に関して、企業の担当者からよく寄せられる質問にお答えします。実務上の迷いや判断に役立つポイントを具体的に解説します。
長いクレーム電話の切り方は?
長時間通話になった場合は、まず「ご要望は十分に伺いました」と丁寧に伝えた上で、以下のように終了の意思を明確にしましょう。
例:「これ以上のお話は業務に支障が出てしまうため、本日はここまでとさせていただきます」
それでも話を続けようとする場合は、「録音しております。これ以上の通話は適切ではありません」と伝え、静かに切電します。
しつこいクレームは罪になる?
はい、内容と頻度によっては犯罪行為となります。特に以下のような場合は刑法に抵触する可能性があります。
- 脅しや暴言 → 脅迫罪
- 過度な繰り返し → 威力業務妨害罪
- 虚偽の情報拡散 → 名誉毀損罪
通話録音や対応記録を残し、必要であれば警察や弁護士に相談してください。
クレーム対応でやってはいけないNG例は?
以下の対応は、状況を悪化させる原因となります。
- 感情的に反論する
- 明確な判断を避けて曖昧な回答を繰り返す
- クレームを放置する(無視)
- 経緯を記録しない(後から説明できない)
- 根拠なく謝罪を繰り返す(責任認定ととられる)
対応の基本は「冷静・記録・線引き」です。
クレーム電話は捕まりますか?
捕まる=逮捕される可能性はあります。特に次のような行為が繰り返されると、刑事事件化することがあります。
- 「○してやるぞ」といった明確な脅迫
- 深夜・休日を問わず執拗に電話する嫌がらせ
- 従業員を名指しで誹謗中傷する
企業としては、被害届や警察への相談をためらわず行うことが大切です。
録音するのは違法じゃないの?
自分が会話の当事者であれば、録音は基本的に合法です(刑法の盗聴に該当しません)。また、録音していることを相手に通知すると抑止効果が高まります。
例:「この通話は、サービス向上のため録音させていただきます」
録音データは、法的証拠や社内教育資料としても有用です。
クレーム電話を拒否するにはどうすればいい?
対応終了を伝えたうえで、着信拒否設定を行うことは合法です。手順としては、
- 一定回数応対し、記録を残す
- 不当要求があることを明確にし、「これ以上の応対はいたしかねます」と通知
- 以降の着信に出ず、必要なら拒否設定とログ取得を継続
※対応終了を社内ルールに明記しておくと安心です。
警察に通報したらどう対応してくれる?
通報内容によっては、警察が注意・指導・調査・警告・逮捕に動く可能性があります。
- 通話録音や記録が重要な証拠になります
- 「生活安全課」が窓口となるケースが多いです
- 犯罪性が高い場合、刑事事件として捜査されます
軽度の場合でも、警察相談ダイヤル「#9110」にまずは相談を。
IVRを導入すると本当にクレームが減るの?
はい、多くの企業がしつこい電話の「減少」と「抑止効果」を実感しています。
- 録音通知やガイダンスによる威圧行為の抑制
- 担当部署への適切な振り分け
- 非対応時間帯の受付自動化で、業務妨害の軽減
導入事例では、現場のストレスが大幅に低下したという声も多数。特にSUBLINE(サブライン)は、小規模な企業でも導入しやすい点もメリットです。
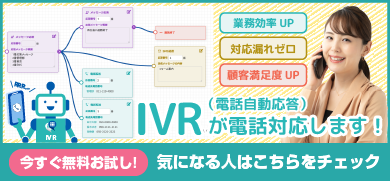
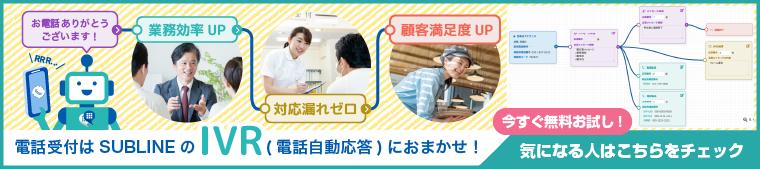
不要な電話対応にサヨナラ!
WEBで完結!無料お試しが可能です!
PROFILE

-
株式会社インターパーク/SUBLINEプロジェクトリーダー・マーケティング担当
中途で株式会社インターパークに入社。
仕事で使う050電話アプリSUBLINE-サブライン-のカスタマーサポート担当としてアサイン。
カスタマーサポートを経て、現在は事業計画の立案からマーケティング担当として事業の推進・実行までを担当。
過去、学生時代には2年間の海外留学を経験。